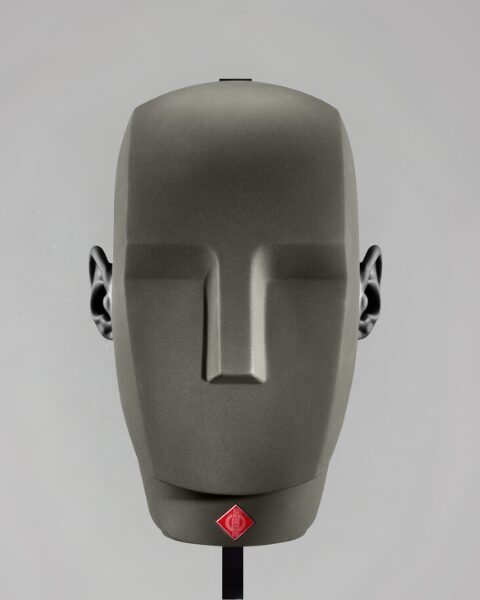買う前に読もう! マイクプリアンプとは?

店頭でもお問い合わせの多いマイクプリ。比較的安価なインターフェースに付属しているものから単体機で数十万円するものまで様々です。マイクと同様にビンテージが重宝されているカテゴリーの製品でもあり、その特徴は千差万別。でも最も重要な音の入口を司る部分だけに慎重に選びたいところですよね。
マイクプリ選びがもっと楽しくなるように、これからマイクプリの歴史や役割や回路の話まで踏み込んで、基礎から学んでみましょう。
お品書き
ミキシングコンソールの歴史から見るマイクプリ

マイクプリが何かということを理解する上で、まずはミキシングコンソールの歴史をおさらいしておく必要があります。
ミキシングコンソールを利用して録音を行っていた時代は、現代の様に単体のアナログ・アウトボードとしてのマイクプリというものはほとんど販売されていませんでした。なぜなら、コンソール自体に各メーカーが技術の粋を集めたマイクプリを搭載されていて、それこそがコンソールのサウンドであり、スタジオのサウンドだったからです。
マルチマイクでの録音が開始された当初より、ミキシングコンソールにはマイクプリアンプが内蔵されていました。モノラルレコーディング時代の代表的な機器がAltec 1788Aではないでしょうか。この丸型のフェーダーノブは、『フェーダーをひねる』という表現で、現代にもその息吹が残っています。たて型のフェーダーでは『ひねる』という表現にはなりませんよね。
その後、ステレオ化、マルチチャンネル化といった方向でコンソール自体も大型化をします。その中で様々な定番と呼ばれるマイクプリが誕生を遂げる事となります。NEVE、API、SSLといった、現在定番と呼ばれるマイクプリが登場、これらは、全てコンソールにビルトインされたマイクプリであったことは忘れてはならないポイントではないでしょうか。
マイクプリとは何か?
マイクプリ(ヘッドアンプ/HA)はマイクで収音した非常に微細な信号を、ラインレベルまで増幅するためのアンプ(増幅器)のことです。
基本的には音声増幅を行う回路なので、ラインアンプなどと同様の回路設計であることが多いのですが、それに比べ増幅量が多いため2段増幅、3段増幅と言った回路構成が取られる場合もあります(60dB以上の高い増幅率を持つ製品も多く見られる)。これは電圧比で表すとなんと1000倍!(60dBの場合)にもなる。これだけ大きく増幅を行うとそれだけ、その回路の持つキャラクターなどが信号に付加されてしまうということは皆さんも想像できるのではないでしょうか。
少々話は逸れますが…
Rock oNユーザーであればWavesのSSL 4000シリーズのプラグインを愛用されている方も多いかと思います。これは絶大な人気を誇ったSSL 4000 Series EとSeries Gのサウンドキャラクターを実機からモデリングしたものです。ちなみに多くのアウトボードの名機(Urei 1176やNEVE 33609など)は、アナログ技術がある意味において頂点に達した70年代に登場していることが多いですね。1982年辺りから商用レコードのはデジタルに移行していきます。
Class Aディスクリートとは
さて、カタログ上でよく見る「Class Aディスクリート」とは何でしょうか。
まずディスクリートとは、IC(集積回路)を使用しないで、トランジスタや抵抗、コンデンサ、真空管などの素子、個別部品の組み合わせで構成した回路のことを指します。パーツ単体でのサウンドキャラクターの追い込みが可能なため、音質へのこだわりの象徴的に語られていますね。機能や、基板の実装面積などを考えればICを利用した回路の方が優位な部分も多くありますが、一つ一つのパーツレベルまで徹底したこだわりを持って回路構成をしていることのアピールだと思って間違いありません。
もう一つ、ディスクリートオペアンプというのが、VPR系の製品を中心に見られますが、これは、OPanp(増幅回路の最小単位)を一つの基板上にディスクリートで構成し、ICの様に決まった端子でソケットに装着できるようにしたものです。

有名なものとしては、API 2520が有りますが、基本的にこの製品のリプレイスとして登場している製品がほとんどです。1万円前後でこのディスクリートOPampは購入することが可能です。増幅回路部分を簡単に交換可能なので、サウンドキャラクターを大きく変化させることが可能となっています。是非ともお試し下さい!!

Purple Audioより。複数の単体パーツを組み合わせてOpampが出来上がる
A or B ?
またClass Aとは回路における増幅素子の働かせ方の一つで、A、B、C、Dのクラス分けができ、その「A」のことを指します。
Class Aは歪みが少なく音質が良いというメリットの代わりに、発熱=消費電力が多いというデメリットを持ちます。その音質故にエフェクターやオーディオアンプに多く採用されています。分かりやすくClass AとClass Bの違いを下記にまとめてみました。
| Class A | Class B | |
| メリット | 歪みが少なく音質が良い | 効率が良く出力が高い |
| デメリット | 電流の消費や発熱量が多い | 電流の消費や発熱量が少ない |
たとえば、Old Neve系で根強い人気を誇るVintech Audio Model 273はClass-A オール・ディスクリート回路を採用しています。
トランスも搭載し、70db(約3200倍)のゲインを持っています。イメージとしては、ディスクリートで構成される素子をパーツレベルで取捨選択することにより、Vintechが追い求めるOle Neveサウンドを実現しているわけですね。
豆知識編(ソリッドステード、カップリングコンデンサ)
冒頭で紹介したSSLのミキシングコンソールは、その名の通りロジック回路制御にソリッドステート(半導体素子=トランジスタや、FETなど)を採用したものです。真空管と比較して、その応答特性などに優れたソリッドステート。半導体素子の進化とともにその特性の向上は目覚しいものがあります。
また、マイクプリにとってカップリングコンデンサは重要なパーツです。
カップリングコンデンサは直流信号を遮断し、交流信号のみを通す働きを持っています。微弱の直流信号が混じっている状態で信号を増幅すると、ノイズ成分まで増幅してしまいます。これを避けるために、次段の入力に送る前に、カップリングコンデンサを通してDCカットする訳です。またここに容量の大きなコンデンサを使用すれば、低域のカットオフ周波数を下げることも可能で、耐圧の高いコンデンサは高域の音抜けが良くなったりするわけです。
しかし回線経路に直列に接続される、カップリングコンデンサーの音質への影響は大きくSSL社では9000シリーズ以降の機種からカップリングコンデンサーを使用しない回路を使い、シグナルへ対する回路の影響を最小化するSuper Analogue回路を採用しています。
キャラクター別マイクプリのご紹介
魅惑の真空管サウンド
マイクプリをはじめ、アウトボードで非常によく聞かれる質問としては、「真空管かどうか?」というものがあります。
価格帯もまちまちで、真空管だから直ちに「音が良い」とか「温かみがある」とは必ずしも言えないとは思います。しかしながら、UADやWavesなど高品位なモデリング系プラグインがその利便性とともに広く普及した現在において、わざわざ数十万円もするアウトボードを導入するのは、やはりハードウェアならではの、オペアンプやトランス、真空管などを経たアナログの音が欲しいからというのは、実は非常に理にかなっています。
真空管の特徴とは、やはりそのナローな特性。お世辞にも良い特性とはいえないのですが、それが逆に「温かみ」、「程よい歪」といったサウンドに寄与します。真空管を利用した回路設計では必須となるトランスもポイントの一つです。
トランス自体もナローな特性を持ち、また歪を生じる素子です。これらの相乗効果によりあらわれたサウンドこそが真空管サウンドであり、未だに我々を魅了するサウンドの秘密なのではないでしょうか。このように真空管の回路は、特性としては、「悪い」要素を多数含みます。ハイエンドの真空管機器では「悪い」要素を極力排除し特性の向上を狙いつつもそのニュアンスを活かす設計の製品も多く見られます。
逆に低コストな製品では、真空管を動作させるために必要なヒーター電圧をしっかりと作らずに低圧で駆動をさせあえて特性を悪化させ歪を取り出している機材も見られます。このような機器は積極的におすすめは出来ませんが、その特性を理解した上でエフェクターとしてご利用いただくのであればいいと思います。

真空管サウンドに徹底的にこだわり、その魅力を最大限伝えるために、自社製の手巻きトランスをはじめとし、フル・ハンドメイドで生産される珠玉のアウトボード・シリーズを発売しているのがManleyです。
Stereo Variable-MUとともにManleyの中でも人気を二分するDual Mono Mic Preampは、コンパクトな1Uラックサイズに、フル・ディスクリートの真空管マイクプリを2ch搭載したマイクプリです。一般的な3極管ではなく、5極管を採用しており、チューブにありがちな粗い歪みのない、暖かみと透明度を両立させたサウンドキャラクターを持っています。ふくよかな中低域、真空管ならではの倍音豊かななめらかな、Manleyサウンドですね。一度はまると抜け出せません。
もう一つの大きな特徴が、その単純な構成。基本的にはゲインをコントロールするだけですが、インプット・アッテネーターとGainの組合せが、シンプルながらも幅広いサウンドメイキングを可能にしています。
Manleyが誇る「バリアブルフィードバック」技術は、出力信号から取り出した微量の信号を、Gainノブを回すことによりユーザーの好みで、入力段にフィードバックできるものです。たとえばインプット・アッテネーターを固定にしたまま、Gainノブを40-60の間で可変させ、好みの(オケに一番適切な)質感が得られるのです。

真空管タイプのマイクプリをもう少し紹介していきましょう。まずは当店でも人気のUniversal AudioのLA-610 mkII。610プリ+EQ+LA2Aスタイルコンプレッサー構成の真空管チャンネルストリップで、真空管らしい角の丸い柔かなビンテージサウンドが特徴です。たとえば、2kHz〜4kHzあたりの耳の一番敏感な中域がピーキーなソースに使用することにより、気持ちよいマイルドなサウンドに変化します。
チャンネルストリップとしても、利きの良いEQ、直感的に操作できるコンプセクションが幅広いサウンドメイクを可能とします。またHi-Z端子を備え、DIとしても使用できます。
Old Neve系
非常によくリクエストされるのが、いわゆる「太い」という言葉で表現されるOld Neveのヴィンテージサウンドです。
AURORA AUDIO GTQ1はOld Neve系でも非常に好評を得ている機種です。特筆すべきは、入力/出力にはそれぞれ、かのマリンエア社の元スタッフが製造しているバランス接続型のトランスを採用しており、非常に豊かでパンチのあるサウンドを可能としているところでしょう。何と入力部は80dBものゲイン増幅を持っており、リボンであれなんであれ、あらゆるマイクでブリティッシュサウンドが得られます。

またRUPERT NEVEは、Neveの名を冠した中でもとりわけ現代的でサウンドメイクの幅が広いのが特徴です。
カスタムトランスを搭載し、72dBのゲイン増幅に対応しています。実はRUPERT NEVE本人は、昨今のハイレゾの盛り上がりより遥か昔から、20kHz以上の可聴域外が人間に及ぼす影響に着目していた人物であり、彼の設計するコンソールやアウトボードにはその思想が密かに盛り込まれています。
Portico 5024 Quad Micは4chの現場で非常に使い勝手の良いマイクプリです。Silkボタンが特徴的で、たとえばヴィンテージ感を加えたいときにはノブ右をひねってアグレッシブなサウンドメイクが可能です。今時のレコーディング、ミキシングにはもってこいですね。
クリーン系
ここ最近クリーン系のサウンドを求める方も増えてきています。最初からというよりは、いろいろと味付けのあるマイクプリを使用してきて、最後にたどり着くことも多いですね。
MillenniaのHV-3Cは、クリーン系で最もポピュラーといっても良いのではないでしょうか。
クラシックホールなどでののワンポイント収録で使用されることも多く、上品でナチュラルな音質が特徴です。音の変化の少ないトランスレス回路を採用、立上がりの速い、ピュアなサウンドが持ち味で、まさにホール収録のメイン用にぴったりです。
いかがでしたでしょうか?歴史や基礎知識があるともっとマイクプリ選びが楽しくなります。目的に合ったあなただけの1台を見つけて見てください!