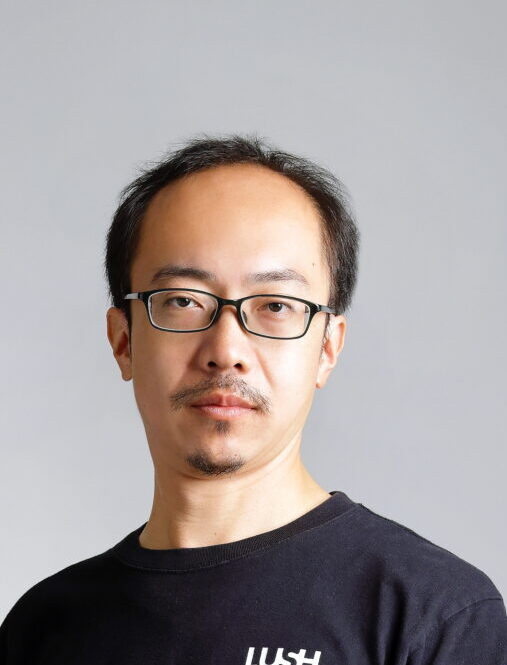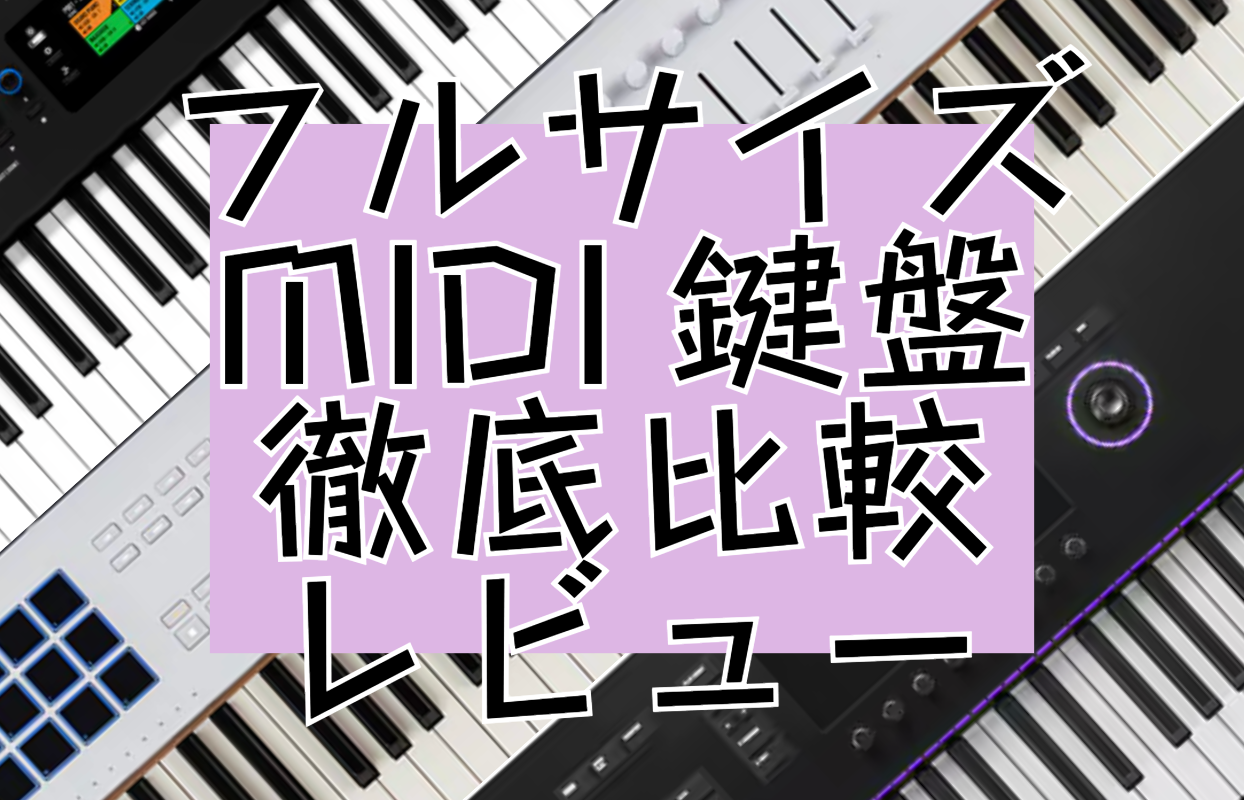beyerdynamicの新しいヘッドフォンDT 1770 PRO MK II、DT 1990 PRO MK IIを試してみた!

最近何かと新製品を書くことが多いPD安田です。さて前回も紹介しましたbeyerdynamic製品のヘッドフォンですが、この度、ハイエンドモデルのDT 1770 PRO、DT 1990 PROに新しいMKIIが登場したので、実際に試していきます。
まずヘッドフォンを選ぶコツですが、前々から言っている通り、下記の点でお気に入りを選ぶとオススメです。
結局スピーカーも然りですが、曲のキー、テンポ、そして全体のジャンル(コンセプト)によって、良い悪いの判断が難しくなってきます。
1,本体の重さ(スピーカーだったらサイズ)
2,付け心地(これはヘッドフォン特有かも)
3,見た目(かっこいいか、可愛いか。部屋に置いてテンションが上がるやつ)
4,値段(気合を入れてテンションを上げるか)
例えば、普段聞いているPOP ROCKのタイトで激しいやつは〇〇スピーカーで聴くとテンション上がるけど、ゆったりな弦楽器バリバリの泣きの曲を聴くとイマイチだな…、でもスピーカー変えたら逆になったな..うーんどっちがいいかわからないかも。ってなります。ちなみに渋谷店でスピーカー試聴いただき、皆さんの聴いている曲を一緒に聴いたりするのですが、人によって意見がバラバラなので、結果としては己の信じた感覚で選ぶとベストです。ご参考までに。
それでは、今回の新しいbeyerdynamicのDT 1770 PRO MK II、DT 1990 PRO MK IIを早速比べていきましょう!
外観は変わった?
まず初めに旧モデルと比較をしていきます。DT 1770 PROの方は一見何が変わったの?っと思いたいところですが、よく見るとキャビネット側はモデル名のロゴの入り方、ヘッドバンドとキャビネットが繋がっている部分のロゴデザインが変わっております。特にここが変わったからと言って音質に影響はないのですが、肝心の音質は、以前のモデルは割と聴き馴染みのある感じで、低域が篭りすぎず、全体を通してややオーディオ寄りな上質さ(これがbeyerdynamicのイメージ)でしたが、今回のMK2からは左右の高域の分離感が増し、以前よりもリバーブ関連の奥行きが見えるようになりました。
なお個人的な意見として、左右の高域感が見えるからといってこれが全てではなく、おそらく多くの方は定位感の的が絞られている環境で聴いている方が多いとは思うので、割とまとまって聞こえる系と広がっている系で用意するといいかもです。別におすすめするわけではないですが、旧DT1770と新しいDT1770 MKIIを2つ持っておくと傾向は違うので、いいかもしれません。
★左がMKII、右が前バージョン


続きましてオープン側のDT1990 PRO MKIIの紹介になりますが、こちらも大きなデザイン変更はないのですが、気孔部分のデザインが変わっており、こちらもサウンド部分のチューニングが施されている設計になっております。また中身も先ほどのDT1770MKIIと同じく、溝が入った設計になっておりました。

音はどうなった?
外観ではこんな感じでしたが、中の部分は変わっており、新しいモデルでは写真のように溝が入っているのが確認できます。もしかすると高域の広がりが増しているのは、ここの構造におけるチューニングが施されているのも影響しているかなと思われます。見た目は大きくは変わらず、加えて重さもさほど変わっておりません。そして付け心地もほぼ一緒になりますので、既存ユーザーで愛用している方は一度サウンドをチェックいただき、評価をいただきたいところです。新規の方は、この傾向のヘッドフォンがあるとどうか!でご検討いただくとベストです。

音質もチューニングの部分を大々的に書きましたが、もう一つ大きく変わった点として、ヘッドフォンの抵抗値が従来ですと250Ωだったのに対し、今回のモデルから30Ωに変更となりました。これによりiPhone直接で聴いても、Vol. Maxでもちょっと小さいかもというのが、だいぶ音量的にも発揮できるようになっております。ただ、オーディオインターフェースにて使用する際は、音量もだいぶ稼げるのであんまり気にしない方もいたかもしれません。抵抗値が大きいほど、プレイヤー側でそこそこ出力が稼げないと、全然聴こえない!とか、プレイヤーによってはMaxにして歪んでしまうとかありますが、これでだいぶ解消され使い勝手も良くなっているかと思います。
さて肝心のサウンド感ですが、DT1770MKIIの高域の解像度の件がありましたが、DT1990MKIIだといい感じに広がりの分散具合が散り、全体を聴くにはいいヘッドフォンではないのかと思っております。多分高域をしっかりと解像度上げるにはオープンにすることで化けるかもしれません。だいぶ今時のサウンドになっているので、これは既存でも新規でも是非に聴いてみて欲しいモデルになります。「DT1990PRO MKII」モデル名を覚えて聴いてくださいませ。
ヘッドフォンは本体の重量をできれば軽くしたいけれども、ケーブル線を細くすると抵抗値が上がり、アンプなどが欲しくなってきます。逆に太くすれば重くはなるが抵抗値を下げれるという、開発者は悩ましいところではあるのですが、今回は抵抗値を下げつつも重量はそこまで変化させておらず、加えて音質もしっかりとbeyerdynamicを保っている点は試聴において重要ではないかなと思います。
以上、内容による比較になりまして、基本的に大きく見た目は変わっておりませんので、既存ユーザーしかり、新規の方もぜひ一度はbeyerdynamicを経験していただけると幸いです!
関連記事