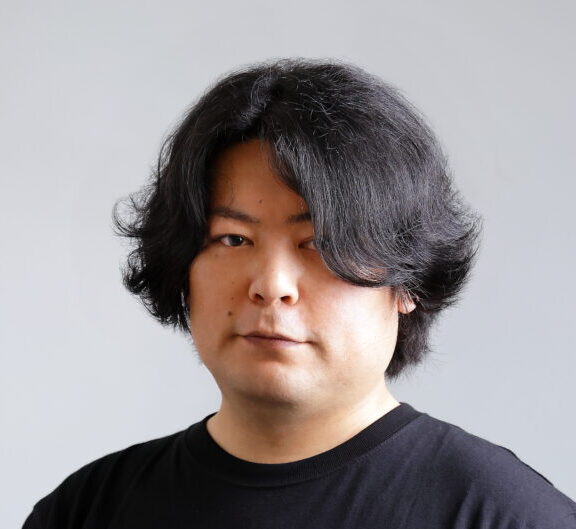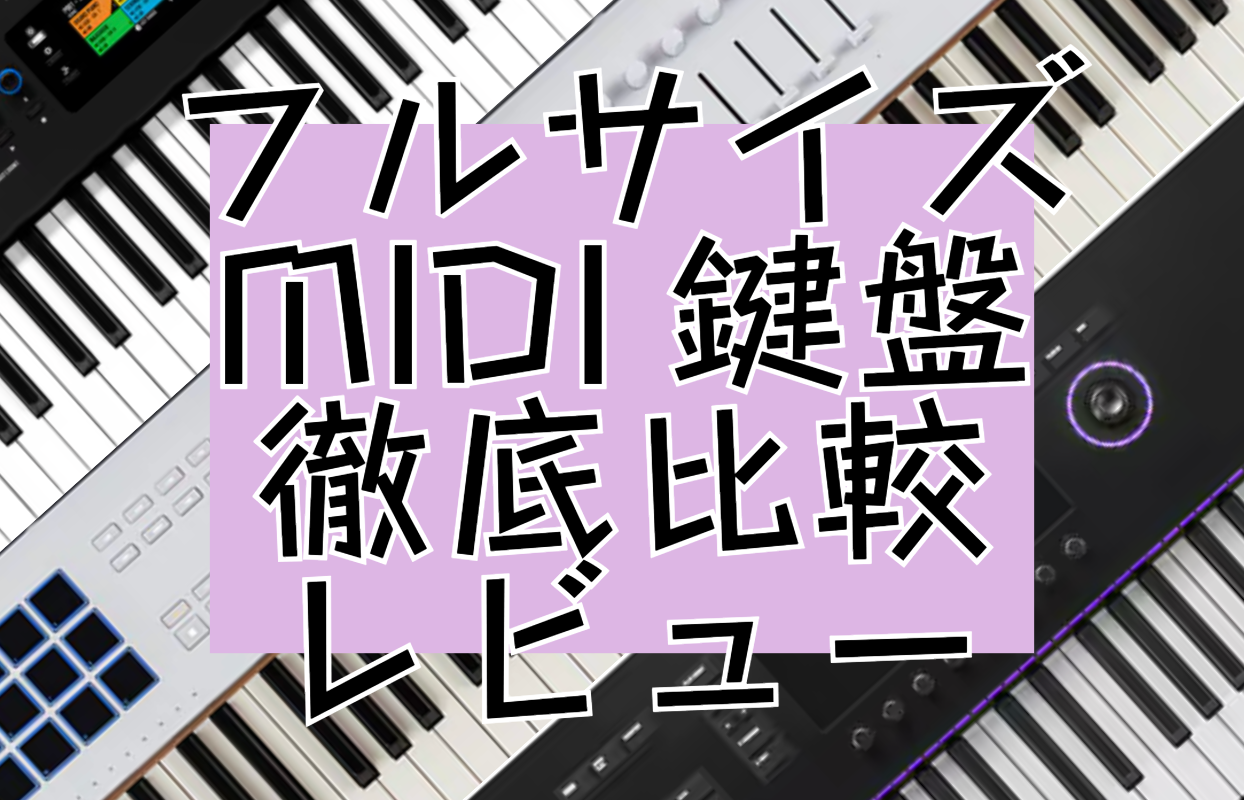クリアにもウォームにも仕上げられる万能マイクプリアンプ!Universal Audio LA-610 MKIIサウンドレビュー

オルタネイト福山が気になった製品を動画レビューする本コーナー!今回ご紹介するのは、LA-610mkII!
私自身初めてマイクプリを導入する際、厳選して購入した思い出深いマイクプリです!その理由をご紹介させていただきます!
はじめに結論から言うと、タイトル通りLAー610MKIIは、クリーンとウォームどちらのサウンドキャラクターにも対応することがオススメの理由となります。
具体的に掘り下げていきましょう!
感想
一番注目していただきたいポイントは、INPUT LEVELとPADの調整によるサウンド変化です。プリアンプ部分は、真空管タイプの製品ですが、マイクプリアンプでのINPUT LEVELを抑え、OUTPUTのGAINを上げるとクリーンなサウンドになります。
逆にあえてPadをいれてINPUT LEVELをぐいっと持ち上げ、OUTPUT GAINを抑えるとチューブならではのキャラクターが際立ち、太く豊かなサウンド変化になっていっているのがわかると思います。
これが、ボーカルなどのレコーディングの際、マイクの音色や楽曲の仕上げイメージに合わせてキャラクターを決める際に1台で対応できるので万能と呼ばれる所以です。
サウンド自体も元のサウンドを大きく変更することなくナチュラルに仕上げられますし、チューブの倍音付加によって、よりブラッシュアップできるようなところが使い勝手がいいですよね。
オススメ使用シーン
ボーカルレコーディングのファーストチョイスとして
機材の性格としては、真空管マイクプリDI+オプティカルタイプのコンプレッサーという組み合わせとなっています。サウンドキャラクターは前述の通りですが、ここに緩やかにかかるオプティカルタイプのコンプレッサーが入ることで、コンプ感の薄いナチュラルな仕上げが期待できます。
※ちなみに、マイクプリ610とFETタイプのコンプレッサー1176を組み合わせた6176というアウトボードもあります。FETタイプは、コンプレッサーの反応速度が速いので、コンプの反応速度重視の場合は、こちらがおすすめです。
ただし、コンプレッサーの効きがわかりやすいため、ボーカルレコーディングや生音の楽器収録で自然に収録したい場合はLA-610 MKIIが適しています。
ギター、ベースレコーディングも魅力的!
HI-Z入力に対応していますが、楽器の収録でも重宝します!ボーカルRECと同じく、クリーンにもウォームにも仕上げられます。特にベースやアコースティックギターなどの収録では非常に満足いただけるでしょう!
コンプレッサーの動作原理について
ここで、オプティカルコンプレッサーが出てきたので、あらためてコンプレッサーの種類を簡潔に解説させていただきます。
シンプルに表現するとコンプレッサーとは、音量を調整する機能です。
その世界は非常に奥深いものがありますが、音量をコントロールすることで何が起こるかというと下記のように様々あると思います。
- 音量を揃えて演奏を安定させる。
- 音量を揃えて、最大音量を上げる。(ピークが高い箇所があるとデジタルクリップするため、音を平均化することであげることができる)
- 音量を揃えることで、迫力を出す!(全体的にボリュームを上げれるため)
- アタックタイムをコントロールして、楽器の鳴り方を調整する。(コンプがかかると基本的に音量が下がります。そのかかり具合でニュアンスを調整します。)
- リリースタイムを調整して、リバーブのように音のテールが持ち上がるように演出する。
などなど効果やニュアンスの違いがありますが、動作方式によりコンプレッサーを使い分けます。
FET、真空管、オプティカル、VCA回路の4種類の動作方式を見ていきましょう!
1. FETコンプ
- FETとは電解効果トランジスタ(Field Effect Transistor)の略で、抵抗による電流の制御ではなく、入力された電圧によって電流を制御するタイプのものです。
- コンプレッサーを動作させる際のアタックタイムが速く、音の立ち上がりの早い音、ドラム、パーカションやギターなどの音量制御に適しています。(※もちろんボーカルもOKです。)
- 設定にもよりますが、コンプレッションがかかっているニュアンスが出やすいです。
- 代表的に挙げられるものはやはりUniversalAudioの1176です。
- レスポンスの早さ、コントロールのしやすさ、クリーンな質感が特徴です。 世の中のメーカーのFETコンプはこの1176をモデルにしたものも多くインプット段とアウトプット段のトランス等の回路によって独特な味付けができるため、オールマイティに使用する事が出来ます。
2 .オプティカルコンプ
- LEDとその受光体であるフォトセルを組み合わせたフォトカプラーという素子を利用して、入力された信号(電流)でLEDを光らせます。そうすると音の大小が光の大きさになり、フォトセル(cdsセンサー)がその光の大小によって電流を発生させます。わかりやすく言えば、フォトセルは太陽電池のようなものなので、光の強さを電力量に変換していると言えます。
- 反応速度が遅く、音量に対しての特性も精密にリニアなものではないが、それが逆にオプティカルコンプレッサーの音、味ともいえます。
- コンプレッサーがゆっくりかかりゆっくり解除されるため、いわゆるコンプレッサーがかかっているな!というサウンド変化が起きにくいため、自然にサウンドボリュームをコントロールできるのが特徴です。
- 繊細な表現を必要とするボーカルや生音のレコーディングに適しています。
- スタジオによくある機材でいうとLA-2Aが代表的にあげられます。Avalon VT-737のコンプ段もこの形式ですね。
3 .真空管コンプ
- 真空管タイプは、サウンドキャラクターがつきやすいとイメージがありますが、私個人の見解としては全く異なります!設定次第では、今回の4種類の中でどの方式よりも繊細に収録するのにおすすめです。
- (言葉では表現が難しいですが)ボーカル収録などをした際、その言葉のディテールなどの表現力はとても繊細で音楽的です。
- 音量制御回路は、通常のアンプとは逆にグリッドへの入力信号に応じた利得(ゲイン)を得るのではなく、レベル検出回路で得られたしきい値(スレショルド)を超えた電力量を元に、負の利得を得るものです。その利得回路に真空管を使用することでコンプレッションが深く掛かれば掛かるほど(負方向のゲインが上がれば上がるほど)、その真空管のニュアンスが出現してきます。
- 半導体と比べ歪みの多い真空管回路ではゲインリダクションが深く掛かった際にサチュレーションが出現するものもあり、それが一つのキャラクターともなっているわけです。
4.VCAコンプ
- VCAとはVoltage Controlled Amprifireの略で、電力で制御されるアンプということになります。非常にシンプルな構成で、アンプの増幅率を外部の電力制御によりコントロール、コンプレッサーではレベル検出回路により得られた電飾がコントロール信号となり、負方向への利得を得るアンプへ接続されます。 この設計を利用することで機器内部のアンプの構成段数を減らすことが可能となります。
- VCA回路はかかりも早く、特にサウンドがクリアという特徴があります。コンプレッサーによるサウンド変化をさせたくないけど、音量を調整したい場合にオススメです。そのため2MIXのマスターにかける場合などに多いかと思います。
- 通常であれば入力段のアンプから制御回路のアンプ、そして出力段のと最低でも3段のアンプを利用することとなりますが、VCAでは入力段側の増幅率をコントロールすることで、入力段と出力段の2段増幅とすることが可能です。
- もちろんすべての回路構成が、このような形ではありませんが、実際の音声信号が通過する経路を少なくすることでピュアな信号を取り出すことが出来るという特徴があります。
- SSLのStereo Bus CompresserやDangerous MusicのDangerous Compressorなどが代表機種です。