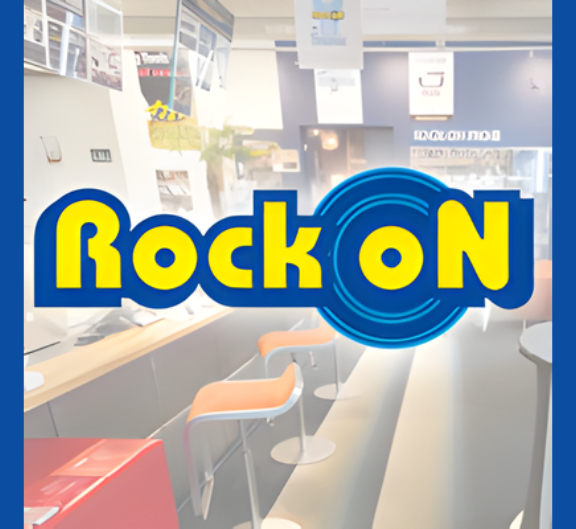MIXに活用出来る ハードウェア・リバーブ特集

突然ですが、みなさんはアウトボードはお持ちでしょうか?
ミックスやレコーディングに使えるコンプレッサーや、トラックの色付け目的にマイクプリアンプなどをお持ちの方も多いかと思います。
今回は、アウトボードとしてリバーブ、それもギター向けのコンパクトエフェクターってどうなの??という実験回です。
ギター向けのエフェクターといえど侮るなかれ。
昨今の機種はステレオIN/OUTは当たり前、高いS/Nを誇り、最大入力レベルも高い物が多く、バランス/アンバランスの問題はさておき、実はDAWのハードウェアインサート用として使いやすい機種が多いのです。
と言う訳で今回は
6機種ほどセレクトしてみました。
各機種のご紹介。
*strymon Bigsky MX
言わずとしれたstrymon。10年以上の時を経てBigskyからBigsky MXにUpdateされました。
前機種のBigskyはそもそもギタリストの足元のみならず、PA側のリバーブとしても見掛ける事が多いです。
特筆すべき点は、圧倒的な高品質サウンドとルーティング。
アルゴリズムの数も相当ながら、深くクリアな質感は、目を開けたまま夢境に飛んじゃう感覚です。
ステレオI/O:対応
最大入力レベル:+10dBu
*strymon Nightsky
先ほどのBigsky MX とは打って変わりこちらは幻想的なシンセシスリバーブ。
レゾナントフィルターや、シマー機能等によってお手持ちの楽器をシンセ化したような変化が楽しめます。
シーケンスもあるので、リズミックなフレーズメイカーとしても優秀!
とりあえず掛けてみると予想外の美しい変化があるのでおすすめです。
*Chase Bliss Audio CXM1978
この見た目は伊達じゃない!
モーターフェーダーなので、プリセット変更に伴いシャッとフェーダーが付いてきます。
Chase Bliss とMeris のコラボ商品です。両メーカー共に空間系エフェクターのセンスの高さは折り紙付き。
見た目からはTCやLexiconなどの「スタジオ系リバーブ」を想像しますが、この2社がタッグを組むくらいなのでどうせ独創的なヤヴァい音がするんでしょうね。ワクワクします!
今回試した中では、唯一バランス入力対応でした。(設定で変更が必要)
ステレオI/O:対応
最大入力レベル:データ無し
*empress effects Reverb
これは私物です。このリバーブ、アルゴリズムの数が半端じゃないです。
個人的にはGhostverbのこれじゃないと得られない、太〜く幽玄なサウンドが大好きです。
今回の趣旨とは関係ないですが、モード変更でマルチトラックルーパーとしても使えます。
ステレオI/O :対応
最大入力レベル:+10.8 dBu (12dB Pad 有効時)
*Universal Audio UAFX Golden Reverberator
みなさまご存知UA。メーカー説明文を読むと「Spring 65 、Hall 224 、Plate 140」なんていう心踊る文字が見えます。これはあれですかね?Spring 65は新規だとしても、Hall 224やPlate140はUAD-2のあのアルゴリズムなのでしょうか?!
ステレオI/O :対応
最大入力レベル:12.2 dBu
*Erica Synth Nightverb
Nightverbはギター向けではありませんが、ちょうど良いタイミングで新製品として発売になりましたので一緒に試しちゃいましょう!
新発売!Erica Synthのリバーブです。これは予備知識なしで触っていきます。
ボディが黒いと音が太そうだなって、思いません?
当店エレクトロン大臣のイタリー多田が言うには、キーを固定してのフリーズが出来たり、ピッチ周りの機能が面白い、との事でした。
ステレオI/O :対応
最大入力レベル:データ無し
SN比:データ無し
接続方法
今回の機種は全てアンバランス入力、アンバランス出力。(CXM1978だけ、モード変更でバランスに対応しています。)
今回はアンバランスアウトを備えたオーディオインターフェイス(MOTU M4)を使用し、エフェクターからのアウトプットはオーディオインターフェイスのD.I入力に接続しました。
バランス出力端子しかないオーディオインターフェイスの場合は、出力端子がTRSであれば、TSフォンケーブルを刺しても問題ない事もありますが、ケーブルの工夫が必要な場合があります。
Empress Effects やChase Bliss Audio の輸入代理店であるアンブレラカンパニー様に分かりやすい記事がございましたので、引用させていただきます。
その他、オーディオインターフェイスの入出力レベルよりも、ペダルエフェクターの方が想定している音量が低いはずですので、送りの音量を下げてちょうどいい塩梅を探しましょう。また、遅延補正にも気をつけて。
それでは早速!!
ドラム、ボーカルに掛けてみました。
こちらの記事で収録した音源を使用しました。
[ハンディレコーダーでバンドを録る時に試して欲しいアイデア]
*録音素材は同じ部屋での一発録りですので、他パートの被りが入っていますがなにとぞご愛嬌
素材協力:丸橋ミケ
楽曲「ゆびきりげんまん」
ボーカル、アコースティックギター:丸橋ミケ
クーパー天野 from 東海道本線ズ :エレキギター
イタリー多田 from 東海道本線ズ :エレキベース
PD安田 from 東海道本線ズ :ドラム
それぞれ感覚で、機種ごとの良さを感じたセッティングにしています。
DAWの録音範囲を決めて、ドライ音から再生しながら徐々にMIX(やそれに類するパラメーター)を上げて録音しました。
*strymon Nightsky
ドラム用はモジュレーションやシマーのパラメーターは特に使用せず、シンプルなリバーブとして使ってみました。TONEセクションのLOW CUTとHIGH CUTは効きがかなり鋭く、シンセのツマミ的な感じで演奏しながらガリガリ動かしたくなります。
結構シンセぽさが出ますね。高域の煌びやかな感じが美しく、必要以上にDECAYを伸ばしたくなるサウンドです。
ボーカル
モジュレーションを深めに掛けて、TONEでのフィルターも深めに掛けてます。
シマーは僅かに上げるだけでかなりハッキリ聞こえます。
個人的にはモノフォニックな素材より、和音のある素材の方がつまみのひねり甲斐がありそうな印象。
これはいろんな楽器やシンセに試してみたい…!
*strymon Bigsky MX
ドラムセッティング
Bigsky MXです。
アルゴリズムはHALLを選択。画像のツマミ通りのセッティングです。
ドラムキット全体の低音域が気持ちよく響くセッティングを探しました。
なんなんでしょう、このゆったりとした気持ちよさと透明感。
約¥115,000-のお値段はコンパクトエフェクターにしてはかなりお高めなのですが、もっとお高い値段のリバーブと全然張り合えちゃうでしょ!これ!とテンションが上がりました。
ボーカル
ボーカルは少し攻めたセッティングで試してみました。
このBigsky MX、なんとリバーブアルゴリズムを2種同時に使用可能なのです!
ルーティングも直列や並列を選択可能。
今回は「CLOUD」と「NONLINEAR」を並列で掛けてます。
CLOUDアルゴリズムはシマーともまた違う、ピッチ系処理を施したサウンドですが、音色への追従がスムーズで、自然なシンセパッドが後ろにいてくれるような心地よいサウンドです。様々なアルゴリズムを試すもオモチャ感一切なし!最高ですね。
*Chase Bliss Audio CXM1978
ドラム
さあ、来ました、CXM1978!
strymon Bigsky MXは展示機はあるのでクオリティの高さは重々知っていたのですが、この機種は展示をしていませんでしたので、アンブレラカンパニーさんにお願いしてデモ機を貸して頂きました。電源を入れて、適当にプリセットを移動するとモーターフェーダーがシュっと動きます。期待が高まります。
深くうねるモジュレーション感が素晴らしいですね〜!!フェーダーを動かしてセッティングを決めるのも楽しいです。
どのアルゴリズムもリバーブ音の抜けが半端じゃなく、MIXフェーダーをちょいと上げるだけで充分でした。
特にDIFUSIONを強めた時のリバーブが迫ってくる感じはぜひ試して頂きたいです!
この質感をギターだけに使うのは逆に贅沢ですね。。
バランス I/Oに対応しているので、DAWとの連携は一番やりやすいですね!
ボーカルのセッティングはこんな感じ。
ドラムでのセッティングよりも気持ちスッキリした音を探りました。
個人的にはBigsky MXと並んで好きな音です。
*Universal Audio UAFX Golden Reverberator
ドラム
お次はUAFX Golden Reverbrator。「HALL 224」を選択肢、A/B/Cから選択可能なバリエーションスイッチはB位置にセットしました。「Small Hall A」というプログラムのようです。
リバーブ音の周波数バランスがほどよく中音域に集まっておりドラムに合う感じがします。
サウンドの感じは確実にUADのあの感じですね!
ただ、このクオリティがギター用コンパクトエフェクターで使えるのは最高!と思う反面、今回の趣旨を考えると「あれ?プラグインあるならプラグイン使った方がいいんじゃないか?」と頭を過ったのは内緒です。
ボーカル向けのセッティングはこんな感じ。
やはり高品質な音、という印象。ハードであるメリットとしては、直感的なオートメーションと、録音用にミキサーを用いているなら、演者への返しようにも流用出来るという点。
オーディオインターフェイスのソフトミキサー付属のリバーブって味気ない事が多いですが、このクオリティのリバーブがあると演者さんのテンションも上がるはず!
そう考えるとApolloシリーズって本当に理にかなってて素晴らしいシステムですよね。
*empress effects Reverb
ドラム
続きまして、Empress EffectsのReverbです。こちらはギター系のエフェクトボード以外にもキーボードや、マシンライブ系の方の機材にも見かける事が多い様な。多彩なアルゴリズムが魅力です。
ドラム向けに色々アルゴリズムを試してみたところ、一番綺麗に聴こえるのがやはりHALL系でした。
このアルゴリズム、ギターに使うとちょっと中低域が濃すぎる?と感じていたのですが、ドラムに掛けてみるといつもの印象がちょっと変わってハイの煌びやかさが分かってきました。
単に自分の使っていたギターのレンジが狭かったのかもしれませんね。。
ボーカル向けのセッティングも興味深かったです。
今回はモジュレーション系のアルゴリズムを選択しました。
今回のジャンルが完全に生バンドだけの楽曲でしたので、もう少しジャンルが変わってくるとまた色々なアルゴリズムを試してみたくなりそうです。
*Erica Synth Nightverb
ドラム
最後は、erycasynthのNightverbです。
黒い筐体に15個の大きめのツマミ、虫系?蛾?のデザインをプリントしていて何やらワクワクな見た目です。
I/Oも写真左側がインプット、右側がアウトプットになっており、これは一般的なエフェクターとは逆の配置でやはりシンセ系の文脈を感じます。
ドラムを再生しながらとりあえず無難なセッティングを探していきます。
LOW-DAMPとHI-DAMPがあるのはいいですね。キャラクターがかなり変えられます。
BASSとTREBLEの2バンドのイコライザーの効きがかなり良く、切れ味ある感じは最初に試したNightskyを思い出します(名前も似てる…)
ボーカルへのセッティングですが、先ほどとあまり変更は加えておらず、今度はFREEZEを試します。
FREEZEの効き方はショートタイムのディレイのリピートを上げたような方向で、メロディ楽器や、トラップ的ビートの「チrrrrrr…」的なショートリピート的なフレーズを狙うのも面白そうです。
音作りのコツが分からないまま、色々プリセットをめくってみると、実に様々な音が飛び出してきて驚きます。
これは慣れるまでプリセットを手直しして使っていくのが吉ですね。そういう意味でもシンセっぽい…
それぞれの音、お楽しみ頂けたでしょうか?
機種やアルゴリズムによって音色はバラバラなはずですが、不思議とどのリバーブ音にも存在感を感じました。
これはDAWから一度アナログで出力していることも関係しているかもしれません。
ハードウェアだからのこの作り込み方、プラグインを複数組み合わせても出てこないアイデアや、個人的には楽器の様に音楽の進行に合わせてツマミをグリグリしていくのも面白いと感じました。
リバーブは他の種類のエフェクターと違って多少癖のある音色やアルゴリズムでも、楽曲に馴染むばかりかテクスチャーを加えるのに役立ちやすいはずです。過度にエフェクティブでも受け入れやすいというか…。
そう考えるとクリエイティビティをほどよく刺激してくれるアウトボードとしては結構お手頃なのかも…ですね!
今回ご紹介した6機種はどれも違う良さがありますが、それぞれに尖った良さがあるので、これはビビっと来た機種を選ぶとよいでしょう!