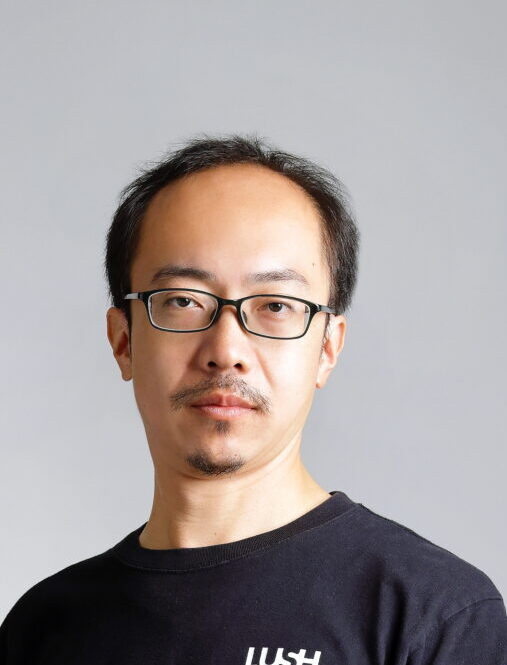Mac、Windowsスペックの見方(by 安田)

ハロー、PD安田です。みなさんご機嫌よう。今回紹介するのは実際に制作を始める方に、必要となるマシンについて説明していきたいと思います。
まず初めにですが、今買い替えを検討している方、そして新規で始めたい方に、私なりに昨今のマシンの販売しているシリーズを見ていくと、最低スペックでも動作においては低スペックでも割と洗練されている機種が多く、昔よりも下手に買ったでも、別に躓かなくなっている気もします。これを踏まえて今私が思う「今後購入するにあたりスペックと予算のバランスポイント」についてですが「どこまで詰め込んだ作品を作りたいか?」によって変わってきます。これはイラスト、動画アニメーション、音楽において共通に言えることで、情報量を多く扱いたいならば”スペックを上げ、予算も多めにとる”という考え方で問題がないかなと思います。
以前に簡易的に音楽や動画を作るなら?ということでMacBook Pro M3(8GBメモリ)でレビューを公開しております。

ちなみに現在でも曲作りしかり、動画など制作するにおいてもこのスペックで問題なく使用できております。ちなみに私はDropboxのサブスクにも加入しておりますので、バックアップの曲データなどはクラウド上にて保管しており、マシン自体の容量は1TBありますが300GB未満程度でそこまでデータは増えなさそうなイメージでおります。さらにパソコンとは同期せず、曲ができて触らなくなったなと思ったらアップロードをしており、理由としては常に同期をすると、Macの容量とDropboxが連動してしまって、マシン本体の空き容量把握がわからなくなるので、このようにしております。
さて、改めての復習ですが、今後導入にあたり見るべきスペックを見ていきたいと思います。
Macの場合

1.CPUはApple Siliconであれば問題なし
まだまだApple SiliconがNativeに対応していないソフトもありますが、今後出てくるであろうMacの新シリーズはApple Siliconだと思いますので、Macを新規で導入されたい方はこApple Siliconの検討一択になります。
この記事を書いた時点での最新はM4(iPad Proに搭載)になりますが、MacBookやMac Studio、Mac ProにおいてはM3のCPUがメインとなっております。そしてMacの場合はメモリをいくつにしたいか?によって、CPUのグレードも変わってきます。なので、ここでは簡単な説明で終わらせますが、iPad Proの方でMacのデバイスと同じCPUを積み始めて来ましたので、以前から予測していることとしては、モバイル端末とデスクトップモデルの統一化を測っているかなと思っております。なのでいずれはiOSがOSを吸収するのか、OSがiOSを吸収するのかは分かりませんが、チップのスペックは高性能も叩き出しつつ、小型、電力からタスク処理の効率化がどんどん進化されていくだろうと思っております。もっと雑に言えばiPhoneでワイヤレスで画面をディスプレイに映し出し、仮想キーボードとマウスでコンテンツをどんどん生み出していくだろうと思うのですが、一応iOSとしては、アプリの複数表示(コンソールやプラグインを別ウインドウで表示する)ができないので、これが解消されるのか、今後もOSとiOSの差別化はあるのか、それとも我々が慣れていくのか。期待したいところですね。さて、本題に戻りますがCPUについては先ほども記載した通り、メモリ次第で選べれるスペックが変わってくるので、続いてメモリ編に移ります。
2.メモリは最低でも16GBは欲しいかも?
8GBでも以前の記事では16トラックの音源が立ち上がり、作曲の作業においては問題ないパワーがありました。ですが、この使い方は使用する音源を絞って、ストレージの容量を食ってしまうサンプル系の音源を多用していないので成り立つ話ではあります。そこで、ストリング関連、オーケストラな壮大なサウンドを作りたいかたは最低でも16GB、24GBは欲しいところかと思います。なおMacの場合、CPUのスペックによっては搭載できるメモリの上限が異なりますので、フルにメモリを積みたい方は、CPUもM3 Maxなどといったランクを上げることになり、予算もそこそこ必要になってきます。
また、アンプシミュレート系プラグイン(元のオーディオ素材から多方面の変化を与える系のプラグイン)や先読み系のプラグイン(マスタリング関連のマキシマイザーやリニアフェイズ系のプラグイン)においては、データのログ情報も多く扱うことになるので、メモリは多めにあった方が安心です。そもそもメモリの役割というのは、実際に再生されるデータの前後を一時保管に使用されたり、Undo/Redoもメモリに入っていきます。戻せる回数が多く設定してある方は必然的に作業すればするほど多くのメモリが必要になってきます。したがって出たとこ勝負、もしくは後戻りをしないスタンスの人はメモリを少なくしても問題ありません。「トラック数を多く扱う方」「音源、プラグインを多用する方」「扱うデータの尺が長い方」に該当する方はメモリを増やせば増やすほどトラブルは少ないかなと思います。参考までに。
3.ストレージは1TBが基準かもしれない
続いてストレージですが、例えば3分のCDクオリティの曲データは大体32MBになります(ステレオ)昔手焼きCDを作られていた方はよく知っている話ですが、1枚につき700MBのデータが入るので、70分くらいの曲が入ります。なお正確に計算する方法としては「1秒x 44100(44.1KHz)x 2(16Bit)x 2(ステレオ)= 176,400 = 176.4KB
3分= 180秒なので 180秒 x 176.4KB = 31.752MB です。
さて、1TBをフルに使えると仮定して、一体何曲のプロジェクトが作れるか?ですが、これも仮の設定で計算してみます。
“48KHz/24Bitのセッションファイルに5分のプロジェクト、ステレオ100トラックを全てステム化した場合”
300秒 x 100(トラック)x 2(ステレオ)x 3(24Bit)x 48000(48KHz)= 8.64GB
になりました。これを…100曲作れば864GBになりますので、1TBで100曲は作れそうですね。ちなみに実際にはトラック全てがステレオはなく、モノラルトラックも混ざっているので1/3くらいが平均的な数字じゃないですかね。そうすると300曲の5分の曲が作れそうです。300曲も作ってたらその頃には次のマシンに買い替えていそうです。
ちなみにイラストの場合はカラーで考えた際こんな感じになります。
3(24Bitカラー)x 2,894 x 4,093(A4ピクセルサイズ)= 35MB
あくまでもこのサイズは結果1枚にした時のサイズですが、多くのレイヤーを重ねることになるので、プロジェクト自体のサイズは書き込み具合で変わります。あとは常に整理整頓を心がけて、無駄なデータも消していただければ、1TBでも問題なく運用できるスペックとなっております。なので、予算を少しでも抑えたいぞ….という方は、常にデータの整理を心がけるといいでしょう。
Windowsの場合
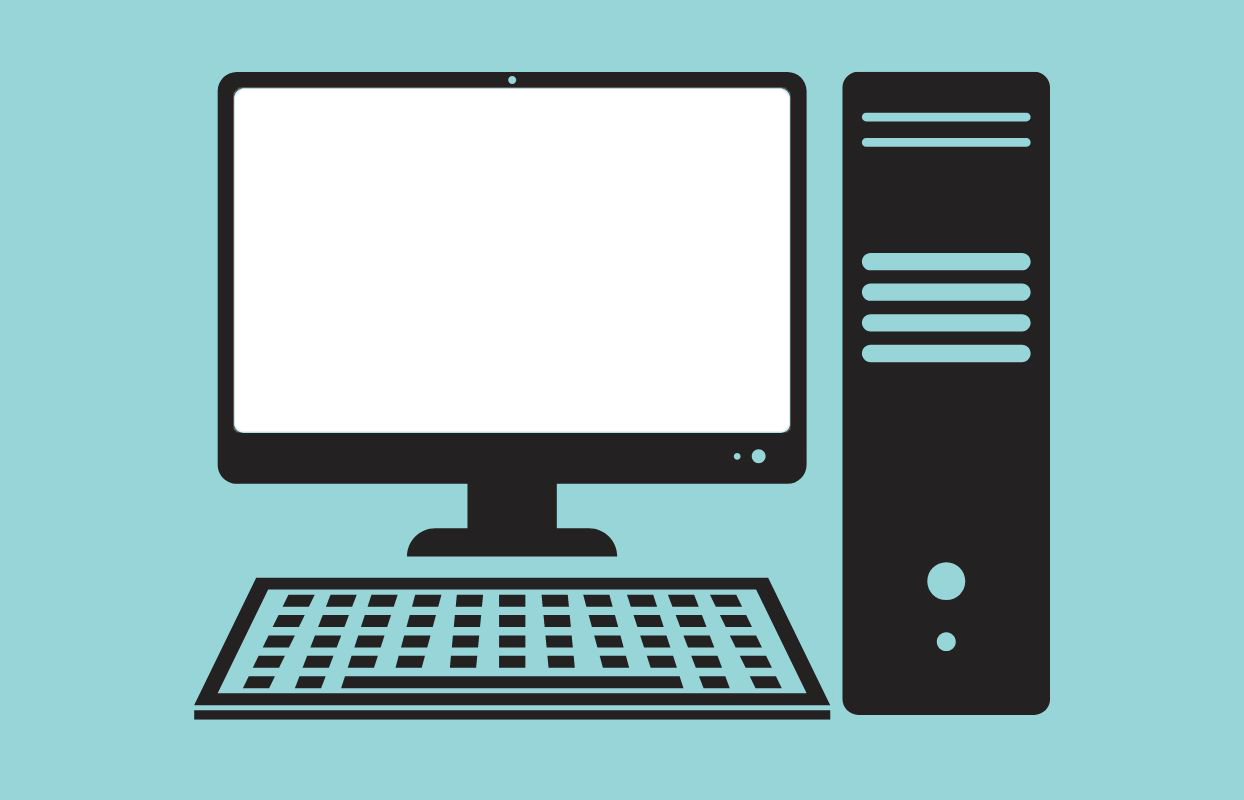
1.CPUの選び方
続きましてWindowsの場合ですが、Windowsの場合は「Intel」か「AMD」の2択があります。基本的に音楽をやる方はIntel製のCPUがベースで考えた方がいいかと思います。一応2020年にAMDの勢いがすごかったのですが、多くのソフトウェアがIntel製ベースに作られている関係で、さらに当時MacもIntel製が主だったこともあり、まだあまり対応も進んでいない印象にあります。多分AppleがApple Siliconをメインにし出した影響もあってか、対応はまだまだ様子見な気がします。従って、基本的にはIntel CPUが搭載されている、中でもCore i5,Core i7のモデルが基本的になりますが、Intel CPUの注意点としては必ずCPUの型番を調べることとなります。大体Windowsの場合アウトレット品や中古市場も多く出ておりますが、この記事を書いた時点では14000番台が最新になっております。
Intel CPUの呼称における説明
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/processor-numbers.html
PD安田が昔から参考にしているサイト(iOS、Android、Macも見れます)
https://browser.geekbench.com/processor-benchmarks
現在は第14世代まで来ており、新規で購入される方はなるべく最新のモデルを購入すると失敗が少ないです。ちなみにMacでも最新のモデルをお勧めしておりますが、特にCPUは年々進化してしまっているので、その基準でOSが更新されたり、ソフト関連もアップデートされてしまうので、導入時は最新モデルがお勧めです。まあ、それなりのCPUが搭載しているモデルを選ぶと実はMacとそう変わらない金額まで上がるので、昔みたいに安く済ませたいならWindowsという考え方はもうないですかね。
Macでも然り、デスクトップか、ノート(ラップトップ)か悩みどころになりますが、案外V-Tuberさんとか、イラストレーターさん関連、もしくは動画クリエイターはデスクトップは多いような印象を受けますが、Macの場合はデスクトップもラップトップも同じCPUなので、予算と持ち運ぶかを前提で選ぶのがいいのですが、WIndowsの場合はデスクトップの方が性能が高いCPUが積んでいるので、同じ予算でスペック良いものを求めたい場合はデスクトップがお勧めです。ご参考までに!
・メモリの選び方
まあ、Macの時と考え方は同じです。多くあれば多くあるほどお勧めでございます。ちなみにWindowsの場合は、カスタムができるモデルが多く、メモリをあとで増やすも可能なので、最初は少し控えめに見て、必要あれば増やすという手段も可能です。Macはその点できないので、ここは両者大きな違いになりますかね。
・ストレージの選び方
続いてWindowsのストレージの選び方ですが、Windowsの場合Macとは違い、ストレージもカスタムで様々な組み合わせで搭載したモデルを選ぶことが可能です。まずその種類についてですが、ざっくり3種類ありまして、そのメリットデメリットを記載すると
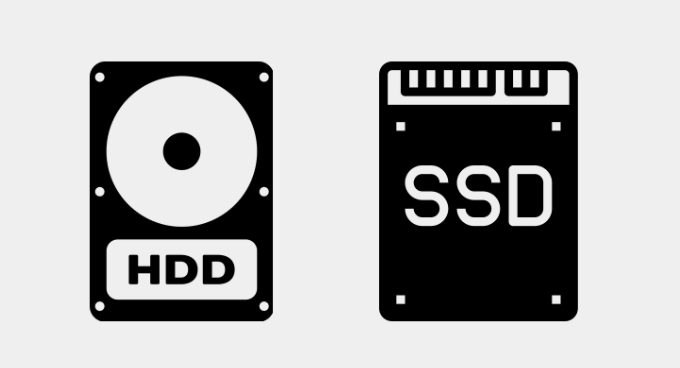
HDD
物理的にディスクが内部で回っており、そこにデータを書き込んでは読み込んでという仕組みになっております。当然物理的に回っているので、振動に弱く、読み書きが遅い。でも安い
SSD
ざっくり言うとたくさんの蓄電池があり、電流を流してそのうち通ったもの、少なかったものの情報でデータの再現並びに、蓄電池に電気を通させる、通りにくくさせる(書き込み)の設定を行う仕組みになります。なので、HDDと比べて物理的に動いているものはなく、小サイズで済むのと、消費電力も少なく、そんでもって軽いです。ただ、HDDに比べてコストがかかるイメージです。
NVMe
接続方法が異なるのが本当にざっくりな説明ですが、Windowsのデスクトップタイプですと、メインのストレージをNVMeにすることができ(拡張も可能ですが)上記の機種よりも読み書きが早いです。ただ、個人的な意見としては、音楽制作において、1セッションで完全にフルオーケストラの音源を一気に読みたい!であれば、NVMeをお勧めしますが、その読み込みの段階で、コーヒーなど入れたい方はSSDでいいかもです。多分みなさん作る時は起動しっぱなしでセッションを再起動は固まった時とか、不在にする時ぐらいじゃないですかね。
なおこの手の違いに関しては、本当に詳しいスペシャリストが別の分野でいますので、私からはそこまで詳しくは書けません。音楽作家は今ではSSDが入っていれば問題ないかと思います。まあ、今時最新モデルでHDDがデフォルトでセットされているモデルはないような気がします。ですが、Windowsの特徴として「メインのOSやソフトのデータにはCドライブに、その他の雑多なデータはD以降のドライブに」というのがあります。ちなみに Aドライブはフロッピー時代のメインOSが入っている領域で、Bドライブが今でいうDドライブになります。いつかこの基準変わったりしますかね。
話は戻しまして、Windowsを選ぶ際はCドライブのメインのストレージが何かと、バックアップ用のHDDもしくはSSDがどれぐらい入っているかを見ていただくとベストで、主な使い方としてはCドライブはOSとアプリ関連、またはデスクトップやダウンロードフォルダに一時保存もの、Dドライブには音源関連や自分の作ったデータを貯めていくというのが一般的な使い方かと思います。Dに関してはオプションで追加したり容量を増やしたりできるのが多いかと思います。ここも予算次第ですかね。
選ぶポイントはOSによる違いはあれど、見るスペックにおいては共通しているので、知識としてはこの3ポイントを抑えておけばいいでしょう。そしてMac、Windowsともに言えることですが、どちらも整理整頓を心がけないと、データが壊れた時に大変な思いをするので、ここも重要視しながら検討していってください。それでは!