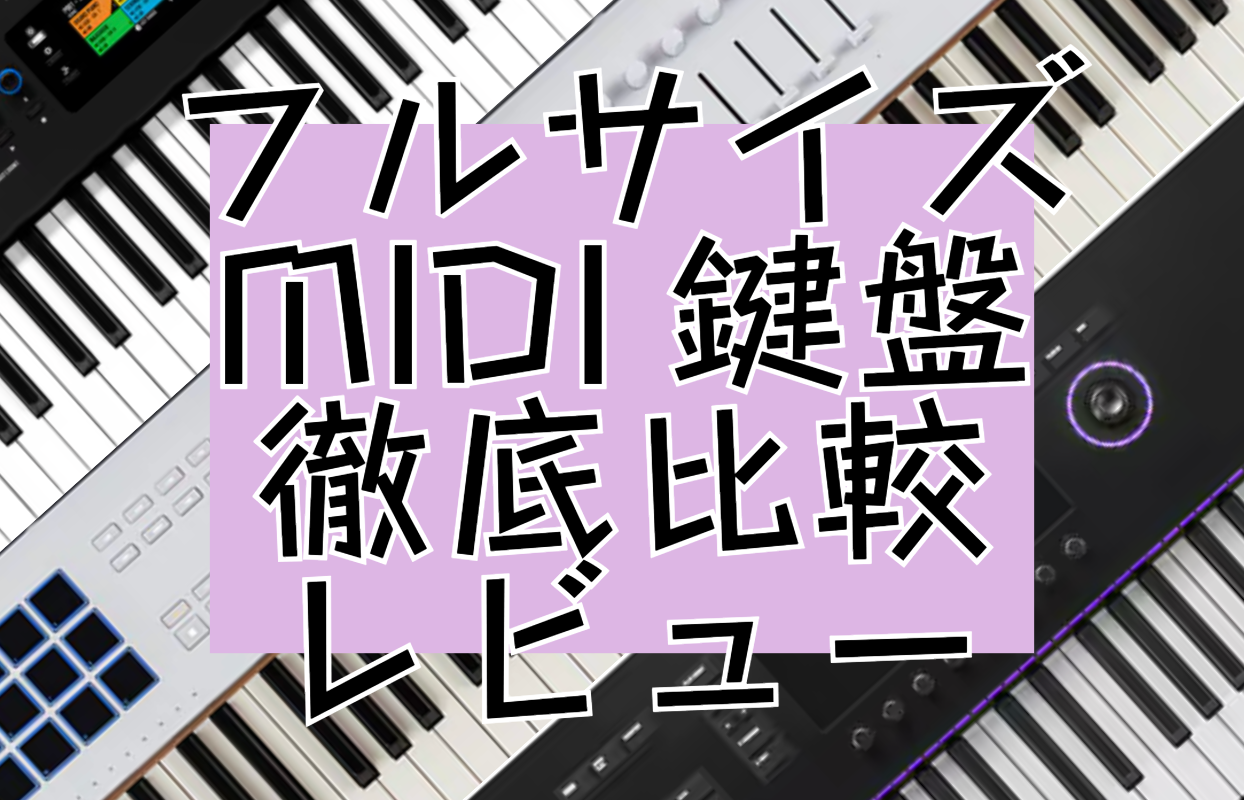AMS NEVE RMX16レビュー!

1.はじめに
こんにちは、スタッフOです。 私は今までギターエフェクターかプラグインでしかリバーブを触ったことがなかったのですが、今回ハードウェアのAMS NEVE RMX16のレビューを担当することになりました!
初めて実機のリバーブを触るので、同じように実機のリバーブを触ったことがない方や、リバーブの実機を導入するか検討されている方に参考になる記事となっています。最後まで読んでいただけると幸いです!
2.RMX16って・・・どんな製品?
RMX16はAPIモジュール規格で3スロット使用したサイズのデジタル・リバーブです。IN/OUTはモノラルインプット、ステレオアウトプットの構成なので、ステレオソースに使いたい場合は2つ揃える必要があります。またリコールしやすいようにセーブ機能も搭載されています。
⚫️主な特徴
- 高性能32ビットDSPプロセッシングと24ビット、48KHzサンプリング、プレミアムA/D、D/Aコンバーターを搭載
- 100dB以上のダイナミックレンジと+22dBuのヘッドルーム
- 入出力レベルの調整が可能で、最適なS/Nパフォーマンスを実現
- 低消費電力
- 各プログラムの基本的な残響パラメータを独立してコントロール
- 選択可能な残響機能のデータをインクリメントまたはデクリメントするためのナッジボタン
- ユニットのメモリーに情報を保存したり、呼び出したりする際に使いやすいように、英数字でプログラムの説明を表示
- すべてのパラメーターと設定を耳で調整できる新しいロータリー・プッシュ・エンコーダー
- 新しいウェット/ドライミックスブレンド機能
- 100個のユーザー定義メモリスロットを備えた新しい保存/リコール機能
- 500シリーズのラック/エンクロージャに対応
仕様
- 幅:114.3mm
- 奥行き:145mm
- 高さ:133.4mm
- 重さ:0.84kg
パフォーマンス
- ヘッドルーム:>+22dBu @ 1kHz (<0.5% THD+N)
- ダイナミックレンジ:112dB @ 24dBu
- 信号対雑音比:82dBu 20Hz – 20kHz +4dB
- 周波数応答:+/- 0.25dB, 20Hz to 18kHz
- 歪み(THD+N):0.002% @ 1kHz (measured at +20dBu, 10Hz to 20kHz filter)
- 一般ノイズ:<-75dBu (20Hz to 20kHz filter)
- ライン入力:インピーダンス ≈20KΩ electronically balanced in slot 1
- ライン出力:インピーダンス ≈150Ω electronically balanced: (L) Slot 1 (R) Slot 3
リバーブの種類
- AMBIENCE
- ROOM A1
- HALL C1
- PLATE A1
- HALL B3
- CHORUS 1
- ECHO A
- NONLIN 2
- REUERSE 1
- REUERSE 2
- FREEZE
- ROOM A0
- ROOM B1
- HALL A1
- PLATE B1
- DELAY
- IMAGE P1
- NONLIN 1
3.基本的な操作
- 「PROGRAM」リバーブの種類を選択
- 「PRE」と「DECAY」プリディレイ、ディケイタイムを操作
- 「LO」「HI」ハイパス、ローパスフィルターの値を設定
- 「IN」「OUT」インプット、アウトプットの量を調整
- 「MIX」エフェクトのドライ、ウェットを調整
4.使ってみた感想
プラグインでしかリバーブを使ったことがなかった自分にとって、ハードウェアというだけで音が良いだろうという先入観がありました。しかしいつものリファレンスを流して聞いてみると、音の説得力と情報量が想像を超えるサウンドで本当にびっくりしました。またリバーブが高級感のあるサウンドを作る上で、重要な役割を果たすことを改めて実感しました。
リバーブは、楽器成分の構成に必要だったり、エフェクターとしての使い方があったりと、さまざまな使い方があります。多くのメーカーからプラグインがリリースされ、それぞれに得意不得意や相性がありますが、本製品はどのソースでも抜群の効果を発揮しました。
基本的な操作が5箇所くらいなので、初めて触る際にもマニュアルを読まなくてもページ切り替えやパラメータの操作が簡単で、実機特有の1パラメーターを動かした際の音の変化がプラグインとは比較にならないくらいダイレクトで非常にわかりやすかったです。
そして肝心のサウンドの特徴ですが、全体的に重心が下がる印象がありました。例えばドラムバスにECHOを10%ほどかけた時は、サウンドに程よい厚みと奥行きが加わり、2mixにAMBIENCEを6%ほどかけた時は、重心が下がるとともに艶がより強調されました。音源の仕上げとして薄くかけるだけでも効果があると感じました。
5.実際の音を検証
シンプルなおかげで、大体の工程は以下のような流れで音作りができました。
- 音源に対してリバーブの種類を選択
- ドライウェットでエフェクト音を調整(DAWのセンド、リターンを使用の場合は100)
- プリディレイ、ディケイタイムを調整
- ハイパス、ローパスの設定
- インプット、アウトプットを調整して適切なS/N調整
今回は3つのソースに対して2パターン+元の音源で検証しましたので、ぜひサウンドの違いを確認してください!
- Drums
- E.Gt(エフェクトのドライウェットによる変化比較)
- 2mix
6.まとめ
どんな人におすすめか
- サウンドに説得力があるリバーブを求める方
- 自分の音源に高級感を求める方
- 音にこだわりたい方
- 500シリーズのシャーシが3スロット余っている方
まとめると、アナログ機材のようなシンプルな操作感で、1パラメーターごとに音楽的にサウンドに変化をつけられる魔法のようなリバーブでした。リバーブはプラグインでも後回しになりがちですが、ここで拘りがあると一気に音源に説得力、高級感が生まれます。
プラグインも良いですが、実機のリバーブもぜひ視野に入れていただけたら、より音源に可能性が生まれると思いますので、ぜひご検討ください!