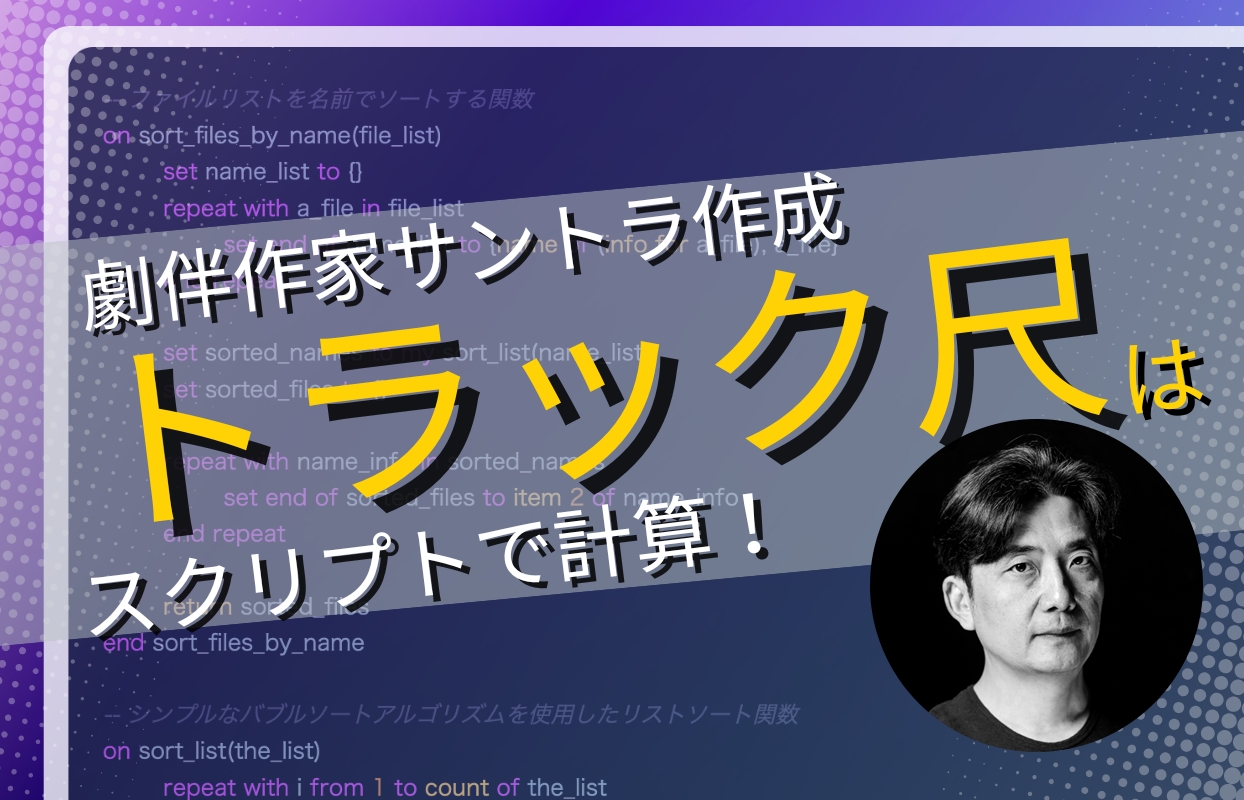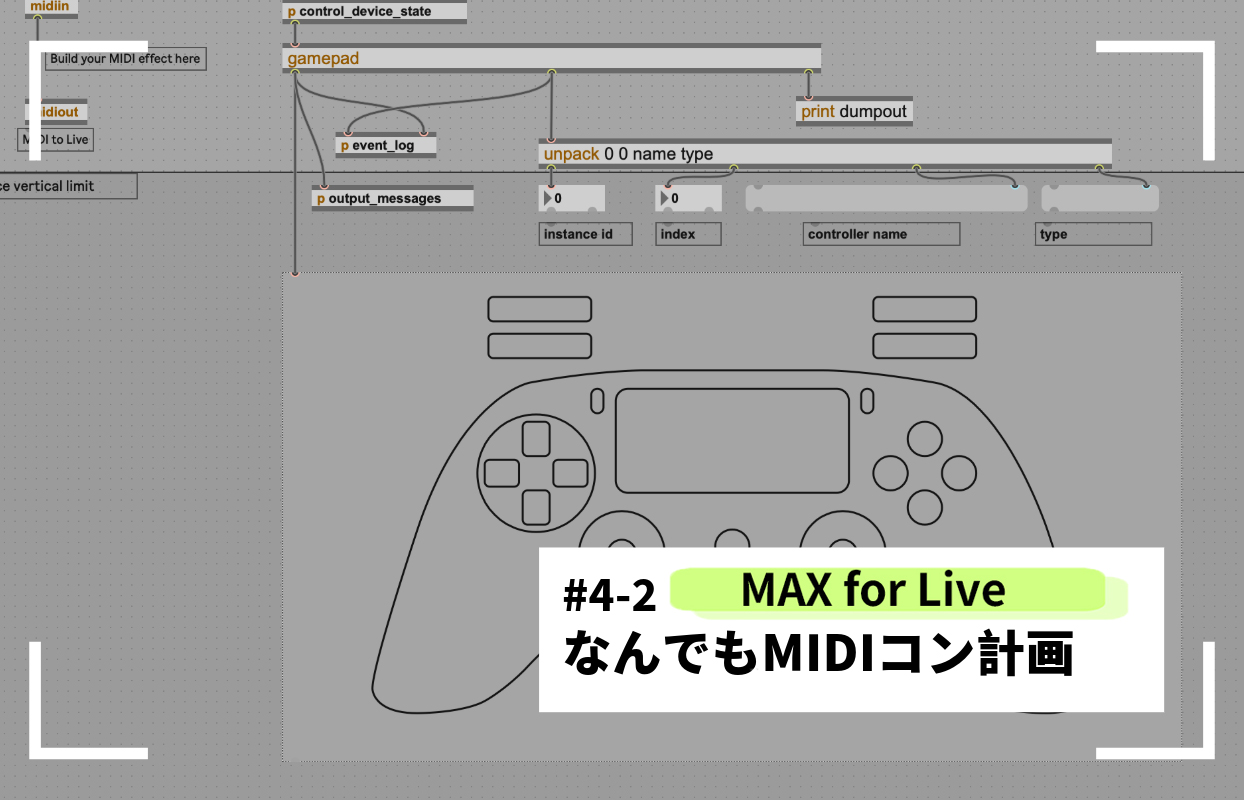瀬川商店第19回:劇伴のプロセスと選曲さん

今回は、選曲さんや音響効果さんと作曲家がどのようにコラボレーションしているかについてお話ししたいと思います。同じ“劇伴”の仕事でも、日本と海外(ここでいう海外は主にアメリカの話ですが)では、映像に音楽を当てるプロセスが少し異なります。
まず、日本のテレビドラマやテレビアニメの劇伴制作では、シーズンが始まる前に「ライブラリー形式」で多くのトラックをまとめて書き下ろします。ドラマなら30〜40曲程度、アニメならそれ以上の数になることも珍しくありません。放送が始まると、選曲さんや音響効果さんが実際の映像に合わせて、その事前に用意されたトラックをはめ込んでいくのです。
そのため、日本のテレビドラマの場合、オンエアがスタートする頃には作曲家の作業はほとんど終わっていることが多いですね。もっとも、最終話まで脚本が固まっていないような作品では、シーズン中に追加トラックを納品することもあります。しかし通常は、シーズン開始後の“音打ち合わせ”(通称「音打ち」)に作曲家が呼ばれることはほとんどなく、そこから先は選曲さんと監督・プロデューサーがやり取りをしつつ音楽の使い方を決めていく形になります。
とはいえ例外もあり、ドラマやアニメでも監督が「このシーンは映像と完全にシンクした音楽を作ってほしい」とオーダーを出す場合があります。そのときは、映像に合わせたシーン単位の楽曲を書き下ろすケースもあるわけです。
一方、アメリカのテレビシリーズでは、作曲家が基本的に毎週、放送される映像に合わせて音楽を制作します。これが日本との大きな違いです。文化の違いでもあるので、どちらが良い・悪いという話ではありません。ただ、もし「劇伴=映像に対して演出を第一に考え、それをサポートする音楽」と定義するなら、映像ありきで作った方がより細かくシンクできるという考え方もあるでしょう。実際、僕が昨年劇伴を担当したアニメ『烏は主を選ばない』では、毎週映像を見ながら音楽を書き下ろしていました。
また、アメリカのコンテンツ制作においては、ミュージシャンの労働組合(ユニオン)の規定で「毎週放送されるドラマ(TV Series)は毎週録音しなくてはならない」という決まりがあります。撮影スタッフなど他のスタッフが連続的に仕事を得られるのに比べ、ミュージシャンだけが毎週雇用されないのは不公平という考え方から来ているようです。このルールがあるため、アメリカでは毎週音楽を録音・制作するのが一般的になったようですが、近年はミュージックライブラリーからライセンスして使用するケースも増えており、すべてが新規書き下ろしというわけではないかも知れません。
では、アメリカ式だと選曲さんはいないのかというと、そうではなく「Music Editor」というポジションの方が担っていることが多いです。アメリカでは監督と作曲家がより密に打ち合わせをする印象が強いのですが、それでも監督の意図をかみ砕いて具体的に作曲家へ伝えたり、逆に作曲家が別の視点を求めたり、シーンによってはステム単位で大胆に編集したりと、コンサルタント的な役割としてMusic Editorが入ることは少なくありません。
少し話が前後しますが、以前、僕が日本のドラマ用に書いた劇伴のトラックをアメリカの音楽プロダクションの方に聴いてもらったときの話です。日本のテレビドラマ用の劇伴は、ライブラリー形式で最初から完結した曲構成(イントロがあり、Aメロ・Bメロと展開して、エンディングがあるような形)が多いのですが、それを聴いたアメリカの方から「これはテレビシリーズ用の曲ではなく、ミュージックライブラリー用なのか?」と尋ねられました。アメリカ人の感覚では「テレビシリーズなら毎週ごとに映像に合わせて書くのが当たり前」という認識なので、完成された形のトラックが並んでいるのは不思議に思えたようです。映像に合わせて書く場合は構成やテンポにバラつきが出るのが普通なので、「ライブラリーっぽい」と感じられたのでしょう。
また、劇伴の仕事でよく耳にするのが「音楽メニュー」の存在です。これは選曲さんが考えてくれることも多く、「これくらいのテンポのアクション曲が6つ、日常シーンで使えるコメディー曲が8つ……」といったリスト的なものですね。特に初めて劇伴を書く作曲家には心強い存在になると思います。僕自身も以前はこのリストに従って曲を提出した経験がありますが、いつの間にか「そっちで好きに書いてね」的な仕事ばかりになりました。多分、僕がメニュー通りに書き進める倫理が著しく欠如していると皆にバレてしまい、音楽メニューありきの仕事が来なくなったのだと思います(笑)。
一方、映画の仕事の場合は、まず編集が済んだ映像を見て、どこにどういう音楽をどこからどこまで使うかを決める「スポッティング」という作業を最初にします。テーマのモチーフをどこに置くか、あるいは意図的に使わないかなどを決める、いわば作曲作業に入る前の設計図づくりですね。特に海外のドラマでは、同じモチーフを何度も使う演出がこの20年あまり多くないので、そこをどうするかといった話し合いも行われます。こうした作業にも選曲さんが関わったり、スポッティング用のセッション(ProTools上の空のリージョンなど)を共有してイメージをすり合わせたりすることがあります。
いつかこのスポッティング作業についても詳しく紹介したいと思っています。たとえばGoogle Sheetsを使ってスタッフと共有したり、音楽トラックのデュレーション&トータルデュレーションを計算する関数を組んで、各楽器の総演奏時間が即座に確認できるようにするんです。3分の曲を1回録音してプレイバックしただけで6分かかりますから、そうした時間を考慮して録音スケジュールを組む必要があるわけですね。
最後に、「フィルム・スコアリングで書きました」という表現を最近よく耳にしますが、これは和製英語なので、そのまま英語にするとアメリカ人には少し伝わりにくいようです。もちろん「UCLAでFilm Scoringを学びました」という言い方は英語でも通じますが、イギリス人やアメリカ人にとっては、劇伴は映像に合わせて書くのが基本なので、毎週書き下ろすこと自体が当たり前の感覚なんですね。
ただ、日本のアニメに顕著な「神曲キター!」という盛り上がりは、同じ曲をいろいろなシーンで何度も流すことで得られる快感でもあります。これはまさに劇伴音楽の醍醐味のひとつです。結局のところ、どちらが良いとか悪いとかではなく、それぞれの文化の違いや、演出方法の嗜好の違いだと感じますね。