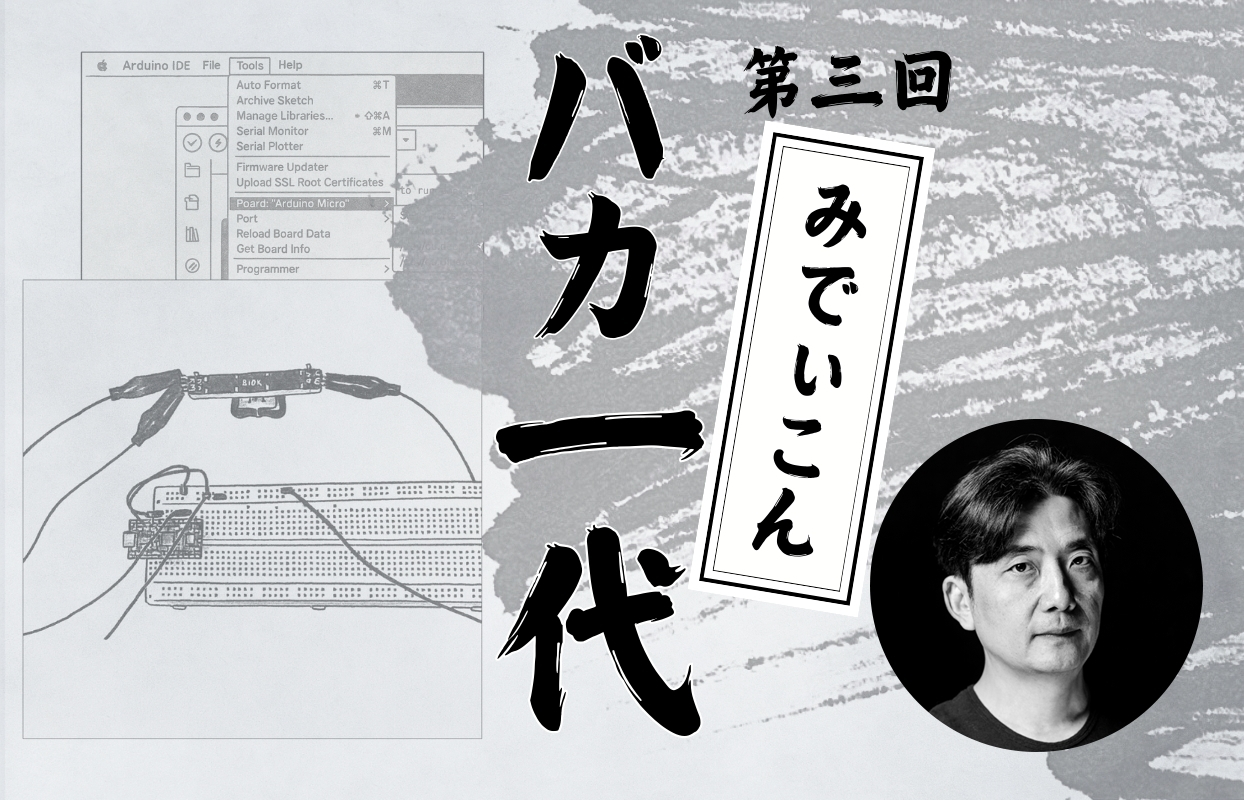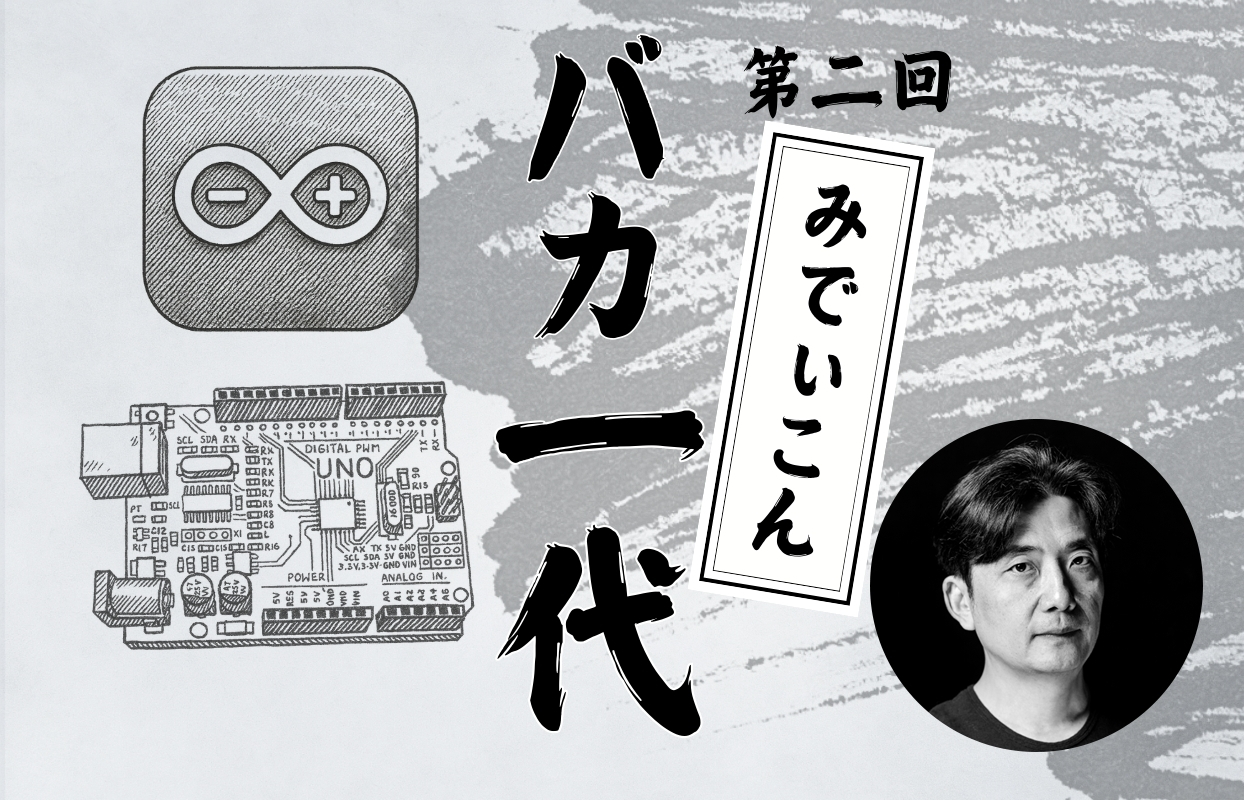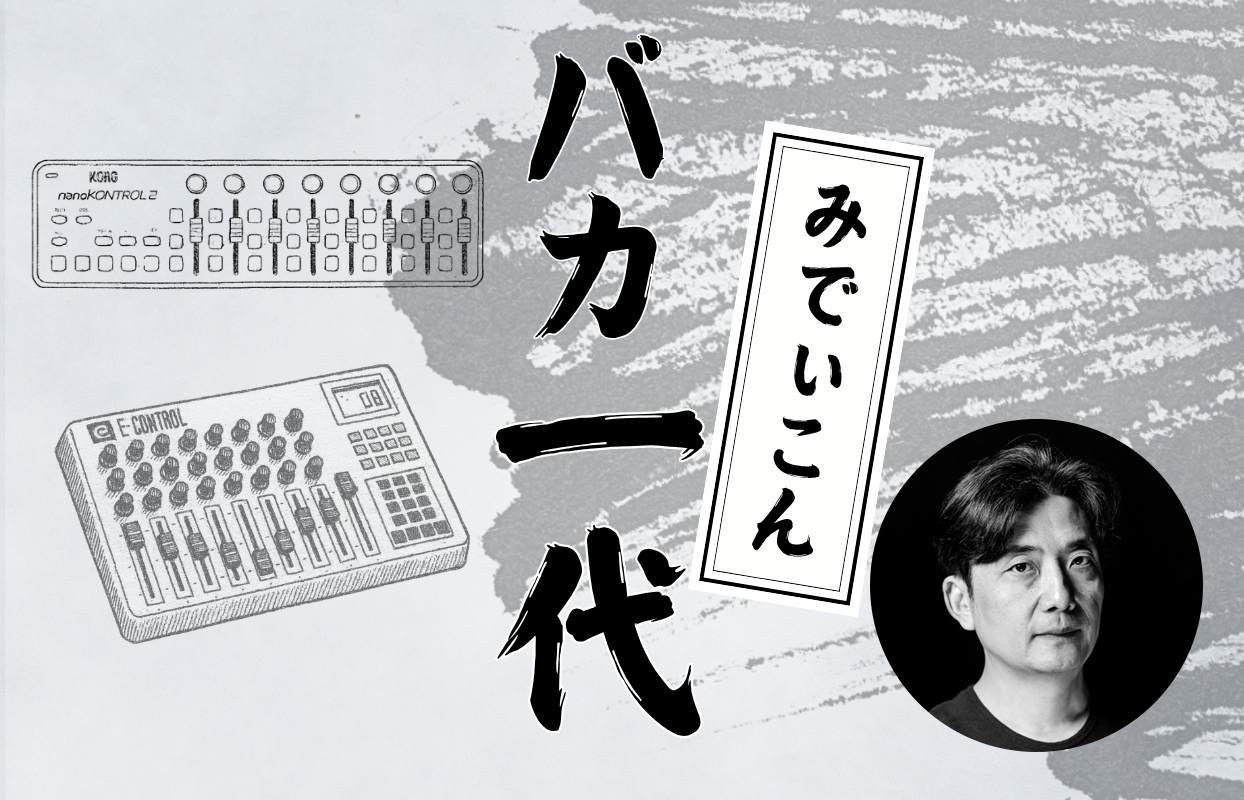Rock oN Company x Acousticfield x CEDAR Audio〜前編〜

みなさんこんにちは、Rock on ShibuyaのVツイン多田です!
Rock oNで働いているスタッフには福利厚生(?)の一環として、店頭スタッフが気になっている製品や技術に対し、定期的にメーカー / 国内代理店の方々を招いて深く学ぼう!という勉強会が開催されます。
今回私たちはAcoustic Field 久保氏をお招きし、ノイズ処理の最前線を駆け抜け続けて37年のCEDAR Audio社のソフトウェア及びハードウェアのDNSを改めて知ろう!という勉強会を開催。気温も内容も熱かったCEDAR Audioというブランドの全貌をご紹介します!
●CEDAR Audioとは?
CEDAR Audio社(英国)は、世界で唯一原音復元技術の研究開発のみを専門に行っている企業です。
映画や放送、音楽メディア、アーカイブ、更には音声資料やフォレンジック用途に至るまで、世界中の多くの作品や活動にCEDARの高品位なノイズ成分除去技術が使われています。
British Library National Sound Archiveの資本により、1988年に設立されて以来、優れたDSP研究で知られるケンブリッジ大学との緊密な関係を持ち、他の追従を許さない世界最高レベルの原音復元技術を提供し続けています。
CEDAR Audio
http://www.cedaraudio.com
・講師紹介: Acoustic Field 代表取締役: 久保二朗 氏
プロフィール
api社のアナログミキシングコンソールから、当時最先端であったDSDおよびハイビットハイサンプリングコンバーターのdCS社など、高品位なプロオーディオ機器を幅広く扱う輸入代理店のセールスエンジニアとしてキャリアをスタートし、その後ライブ、ホームシアター、ヘッドフォン、さらには研究開発分野における立体音響システム開発など、あらゆる音のフィールドに携わる。
2007年、株式会社アコースティックフィールドを設立。
現在まで立体音響を中心とする多くの特殊音響システム開発やコンサルティングを行う一方で、豊富な経験を軸にサウンドアーティストの立体音響による音楽制作やインスタレーションを技術面からサポートしている。
2014年、ヘッドフォンおよびイヤフォンでの音楽リスニングに特化した高音質バイノーラルプロセッシング技術「HPL」を発表。
2020年より、音楽を”作る””聴く”ための新しい環境作りの一つとして、立体音響の普及を目指したワークショップ「立体音響ラボ」を展開。
ロックオン: 久保さん本日は宜しくお願いします!
久保氏: よろしくお願いします。
ロックオン: 早速ですが、CEDAR Audioというメーカーの歴史をご紹介いただけますか?
久保氏: CEDAR Audioは1988年に設立されて、元々研究機関や大学で色々な音声のアーカイブをするにあたって、貴重な資料を整備する復元技術の研究としてスタートしています。最近はちょっと音楽にも使えるツールも出てきたんですが、基本的にはノイズ処理だけを専門にやってきている、珍しい会社です。
ロックオン: 放送局御用達のイメージが強いですが、ラインナップ的にはレコーディングや配信の分野でも強力なツールとして使えるものばかりですよね。
久保氏: CEDAR社をご存知の方っていうのは、放送業界でかなり業界歴が長い方が多いと思います。他社のプラグインメーカーは、いろんな音声処理ができるプラグインを扱いつつ、その中でノイズ除去プラグインも出しています、みたいなラインナップになっていると思うんですけど、CEDARはノイズ処理を行うプラグインだけですので、かなり珍しい会社だと思います。
ロックオン: DSP技術も凄く、ハードウェアも昔からありますよね。
CEDARの歴史: 1990年代
久保氏: 1990年代はハードウェアが主流でした。CEDAR20、CEDAR for Windows とかもありまして、これらはプラグインみたいなものがそのホストコンピューターに入って、ハードウェアにはDSPボードがあって、という専用のワークステーションとして稼働していました。
それ以外のプロセッサーは用途別に全部単体のハードウェアになっていました。例えばDeclickだったら、Declickという1Uのハードウェアがあった、という感じですね。
ロックオン: 1990年代のその時点で、CEDARの処理はリアルタイム処理だったんですか?
久保氏: 最初からリアルタイムですね。そういうものがハードウェアで全部あったんです。このSeries X ってのがそれなんですけど。
CEDAR Series X and Series X+ (1997-2004)
久保氏: 僕もこの辺の後半ぐらいからCEDARを扱っているので、会社もですけど僕個人も付き合いとしてはもう20年、30年近いってことです。怖いですね。。
ロックオン: 海外プラグインやハードウェアを日本国内で取り扱うに際して、1社が継続して代理店業務を続けられている事、これほど力強い味方はいませんよ。
CEDARの歴史: 2000年代①、DNSシリーズ
久保氏: 2000年代に入って、DNS1000が登場し、声以外の暗騒音を抑えるハードウェアが登場しました。こういった機械は過去に無く、ものすごく世界で広まりましたね。
ロックオン: DNS! 本日持って来て頂いたハードウェアのDNS2のルーツですね!世界的に広まったのも、やはり放送業界ですか?
久保氏: 映画やドラマですね。これらのセリフって、音楽と違ってロケなどでボソボソと喋ったり、マイクがオンじゃない場面もあって、SNが悪い中さらに声が小さい事もあるんですよ。
ロックオン: 1980年代の映画はノイズが目立ち、小さな声で喋るシーンでは声を前に出すために過剰に圧縮したり、響かせたりしていたんじゃないかと思います。昔の作品を当時のまま聞くと、騒音でセリフが埋もれてしまったものも少なくありません。
久保氏: そういうとき、映画館で明瞭に聞かせようとするとフェーダーを上げざるを得ないけど、そうするとノイズも全部上がってしまって背景が汚くなる。
DNSが登場したことで、”バックのノイズだけ”を抑えるという発想が生まれたんです。
ロックオン: ノイズの『除去』というところでなく、『抑える』というアプローチなんですね。
久保氏: そうなんです。DNSは除去ではなくレベルを抑えるだけ。映画やドラマでは背景の暗騒音もシーン作りの一部なので、ゼロにしてしまうと不自然になる場合がある。シーンと合わない場合はゼロにしても良いけど、そうでなければ残す。この調整をフェーダーで直感的にできるのがエンジニアにとって扱いやすかったんです。
CEDAR DNS1000 dialogue noise suppressor (2000-2007)
久保氏: 日本でも東宝やNHKのドラマスタジオで導入され、DNSシリーズは有名になりました。アカデミー賞の技術賞も受賞し、この製品の登場で映画のセリフが格段に良くなったと言われています。
ロックオン: ちなみにお値段の方は、、、
久保氏: 当時の価格は100万円ほどです。
ロックオン: 良いお値段しますね〜、ですがそれ以前はノイズだらけでアフレコするしか方法がなかった世界を考えると、革新的で唯一無二。お高いとはいえ、十分に価値がありますね。
久保氏: 高いけれど高価である、イコール高い価値がある、という事は、現行ラインナップのCEDAR製品をご検討されているお客様へ必ず伝えておきたいです。
DNSを使う人はリピーターになり、スタジオ増設時などにも必ず導入される位置づけの製品になりました。先ほどの、「これぐらいならスルーしようかな」というノイズも素早く処理できますので、日常的に使うと考えればコストパフォーマンスは悪くないと感じられると思います。
CEDARの歴史: 2000年代②、Retouchの登場
久保氏: これまではDNSを解説してきましたが、2000年代に「Retouch」という製品が登場します。RetouchはDNSと並ぶCEDARの柱の様な製品で、今もあるハードウェアのCambridgeに入っていた物のソフトウェア版になります。
ロックオン: 見た目は今時の””スペクトラムを用いてノイズを目で見る””タイプですね。
久保氏: Retouchは音声のスペクトラムを見ながら処理するもので、現在のオーディオリペアツールの元祖となる製品です。使い方はシンプルで、不要な部分を囲ってプレビューして、聴いて良ければ『Apply』で処理。その処理速度は非常に速いです。
-久保氏の実演-
皆様へは、久保氏のXポストをご紹介します
ロックオン: 無茶苦茶速いですね!
久保氏: だから「これぐらいならスルーしよう」と思っていたノイズも、手軽に取れるようになり、使用頻度が増えます。
CEDARの歴史: 2010年代〜現在
久保氏: 2010年代にプラグイン版「CEDAR Studio」がリリースされ、Pro Toolsで直接使えるようになりました。
*Retouchはスタンドアローン製品で、ProToolsではAudioSuiteでご利用いただけます。
久保氏: 特にロケ現場などで下処理しておけば、その後の作業が早く進むため、納品スピードの面でも価値がありますし、勿論最終的な作品も良くなりますよね。
ロックオン: 他社のノイズ除去ツールって、アプリの中にサージカルなツールがたくさん並んでいて、その中からAのツールとBのツールを選んで、、といった、いくつかの工程を踏みますが、操作感、操作スピードが全く異なりますね。
久保氏: 海外では合理的に「本編ミックスがメイン、ノイズ処理は下準備」として短時間で済ませる傾向があり、日本のように細かい機能を好む文化とは違います。
CEDARのアドバンテージは、単に「ノイズが取れるかどうか」ではなく、取った結果のクオリティや、処理スピード、判断の早さにあります。例えば「これは無理」という素材の見極めもすぐできるので、取れるかどうかわからない音に何十分もかけて試行錯誤する必要がない。これも作業コストの削減につながります。
ロックオン: CEDARは前後のサンプルを取る作業で微妙にソフトを触るくらいで、基本的にはほとんどワンクリックに近いですね。
久保氏: Retouchは不要音の前後をサンプルし、それを基準に処理します。最初はかなりざっくり囲んで大丈夫です。必要に応じてサンプルエリアを調整したり細かくズームして加工するのが使い方ですね。それ以上の説明が出来ないくらいシンプルです。
ロックオン: この後ハードウェアのDNS2のデモに移りますが、他のプラグインで久保さんのオススメはありますか?
久保氏: iconsシリーズですね。Voice EX2にはSTAGEVOX(ライブ用)、SCREENVOX(セリフ用)など用途に合わせた派生版もあります。声以外をノイズリダクションしたいのであれば、ほとんどのケースでいずれかのプラグインを使用すれば問題を解決できます。また特定の周波数帯域のみノイズを抑えたい場合はDNSのプラグイン版を使用する、といった使い分けができます。
icons シリーズとは?
従来の「プロダクションシリーズ」に、CEDAR Quantum™ と名付けられた新たなアルゴリズム技術によるnear-zeroレーテンシーを実現した「ライブサウンドシリーズ」が加わり、より幅広い用途においてCEDARの最高級ノイズリダクション&レストレーションを実感することができます。
勉強会を終えて
古くからCEDAR Audioの存在をご存じ/ご愛好いただいている方には”いい時代になったなぁ〜”と思う事必須の、歴史を振り返りながらの勉強会でした。
当時の価格が本記事に度々出てきましたが、3桁万円のバジェット、令和の現在は不要です!2025年の春頃に色々お求めやすくなりました!!
また、その昔はデモの申請をCEDAR Audioにお願いして、デモライセンスを付与して貰う、、というやり取りが必要でしたが、これも無しでデモ版がゲットできます!
現在はCEDAR Audioの本国サイトから14日間のトライアル版がダウンロードできますので、触ってみたい方、購入を検討している方は今すぐこちらをクリック!
https://www.acousticfield.jp/cedar-icons
CEDAR Audioの理念を深く学んだ上で、後半はいよいよハードウェアモデルである、DNS2を実際に触ってみます!
後半へ続く!