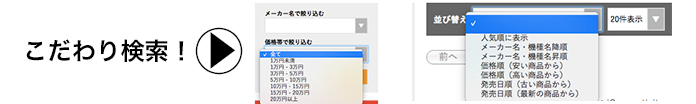PC周辺機器
機材の増設や制作環境のアップグレードに
音楽制作機材に向いた、SONNET Technologyや、OWCなどの定番ブランド製品をはじめ、ストレージ、PCIeシャーシーや、Thunderbolt接続デバイスなど各種取り扱いしております。
OWC Envoy Pro miniシリーズ
ポケットサイズ、フルSSDパフォーマンス。最大946MB/sの速度。
Mac、PC、iPad、Chromebook、Androidタブレット、SurfaceデバイスのUSBまたはThunderbolt(USB-C)ポートでプラグアンドプレイ可能です。
OWC Envoy Express おすすめ!
モバイルにも最適、Thunderbolt™認証取得のNVMe SSD用のバスパワーDIYエンクロージャー。
最大1553MB/sの速度。
OWC Envoy Pro FXシリーズ
防塵・防水・耐衝撃の仕様。ThunderboltとUSB両対応のユニバーサルポータブルSSD。
Mercury Elite Pro Mini 0GB Bus-Powered Storage Enclosure
2.5インチSATAドライブ用のUSB-Cバスパワー外付けストレージエンクロージャ
OWC Express 4M2 (ケースのみ)
4つのM.2 NVMe SSDスロットを搭載したMac&Windows両対応の外付けドライブ。
OWC Express 4M2(ケースのみ、Softraid XT付き)
4つのM.2 NVMe SSDスロットを搭載したMac&Windows両対応の外付けドライブ。Softraid XT付き。
※Softraid XTとは、高性能ストレージ機器で RAID を構成するための Mac OS X/macOS 向けアプリケーションです。
OWC Gemini シャーシのみ
デュアルドライブと、SD4.0カードリーダを含む7つの接続ポートを備えているThunderbolt 3 ドッキングステーション
OWC Thunderbay 4 mini (ケースのみ)
2つのThunderbolt 3ポートを備え、2.5インチドライブを4台収納できるHDD/SSDドライブケース
OWC Thunderbay 4-mini TB3 (ケースのみ、Softraid XT付き)
2つのThunderbolt 3ポートを備え、2.5インチドライブを4台収納できるHDD/SSDドライブケース。Softraid XT付き。
OWC ThunderBay 4 (ケースのみ、Softraid XT付き)
Windows・Mac対応のフラグシップRAIDエンクロージャー
OWC ThunderBay 8 (ケースのみ)
Win・Mac兼用の8ベイのThunderbolt 3ストレージソリューション
OWC ThunderBay 8 (ケースのみ、Softraid XT付き)
Win・Mac兼用の8ベイのThunderbolt 3ストレージソリューション。Softraid XT付き。
OWC ThunderBay Flex 8 (ケースのみ、Softraid XT付き)
MacのためのThunderbolt 3ストレージ。業界初のThunderbolt 3ストレージ、ドッキング、PCIe拡張の3-㏌-1ソリューション。Softraid XT付き。
Blackmagic Cloud Store Mini 8TB
グローバル同期に対応した高性能ネットワークストレージ(8TBモデル)
Blackmagic Cloud Store 20TB
グローバル同期に対応した高性能ネットワークストレージ(20TBモデル)
Blackmagic Cloud Pod
USBディスクをネットワークストレージに変換するデバイス。今お持ちのUSBディスクを流用可能です。
Blackmagic MultiDock 10G
超高速ラックマウント式4スロットUSB-Cディスクドックで、メディアディスクから直接編集!
OWC USB-C Travel Dock E
外出先での接続、充電、表示、インポートに最適なバスパワーの6ポートのミニドック。
OWC Thunderbolt 3 mini Dock
映像出力の拡張用途に便利。2つのHDMI2.0ポートを介して2つの4Kディスプレイ(最大4096 x 2160 @ 60Hzの非圧縮解像度)を接続できます。
OWC Thunderbolt Go Dock
かさばる重い電源アダプタを必要としない、初のフル機能搭載のThunderboltドックです。ThunderboltおよびUSB-CのMac、PC、iPad、Chromebook、Androidデバイスに簡単にすべてを接続して、どこにでも行くことができます。
OWC Thunderbolt Hub 人気!
Thunderbolt 4ケーブル1本で複数のThunderbolt/USB機器を同時接続
OWC Thunderbolt Dock 人気!
3つのThunderboltポートと4つのUSBポート、Apple M1 Macにも対応した最新のThunderboltドック
OWC Thunderbolt 3 Pro Dock
Mac・Windows両対応の10ポートのドック。
SONNET TECHNOLOGY Echo III Desktop
3枚のフルレングスPCIeカードをThunderbolt4或いはThunderbolt3ポート搭載コンピュータに接続できます。
OWC Mercury Helios (PCIeカードなし)ラップトップまたはスペースに制限のあるMacまたはWindows PCデスクトップコンピューターに外部PCIeスロットを追加する拡張ソリューション
OWC Flex 1U4
タックマウント型のストレージ拡張デバイス。4ベイ Thunderbolt™ ストレージ、ドッキング、PCIE拡張ラックマウント・ソリューション。
4ベイ、ストレージ、ドッキング、PCIe拡張ソリューション。SATA/SASやU.2/M.2 NVMeドライブで、最大128TB の容量と最大2750MB/s。パソコンに85Wの電力を供給可能。
SONNET TECHNOLOGY xMac Studio / Echo III Module
Macスタジオ用3スロットPCIeカード拡張システム
SONNET TECHNOLOGY DuoModo xMac mini (Intel & M1) / Echo III Rackmount
Mac miniと一緒にPCIeカードやeGPUを収納する拡張システム
Avid HDX THUNDERBOLT 3 CHASSIS,DESK
HDXカードのために作られたTB3対応専用シャーシ。デスクトップタイプ。
Avid HDX THUNDERBOLT 3 CHASSIS,RACK
HDXカードのために作られたTB3対応専用シャーシ。ラックタイプ。
AKiTiO Node Titan(PCIeカードなし)人気!
Thunderbolt 3対応 グラフィックボード向け PCI Express 外付け拡張ボックス
OWC Aura P12 Proシリーズ
フラッシュメモリ用に設計したNVMeテクノロジーを使用して、速度と信頼性を完全に兼ね備えたSSD
OWC Aura P13 Proシリーズ
ウルトラブック、ノートPC、AIOコンピューター、Chromebook、ミニPC、外付けドライブ向けの最速のNVMe M.2SSDソリューション